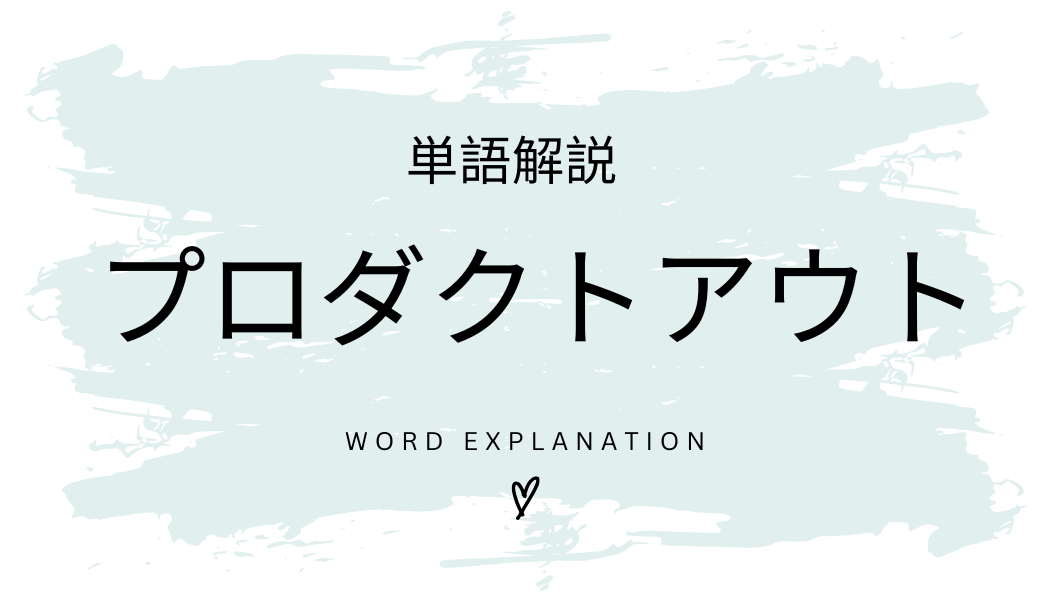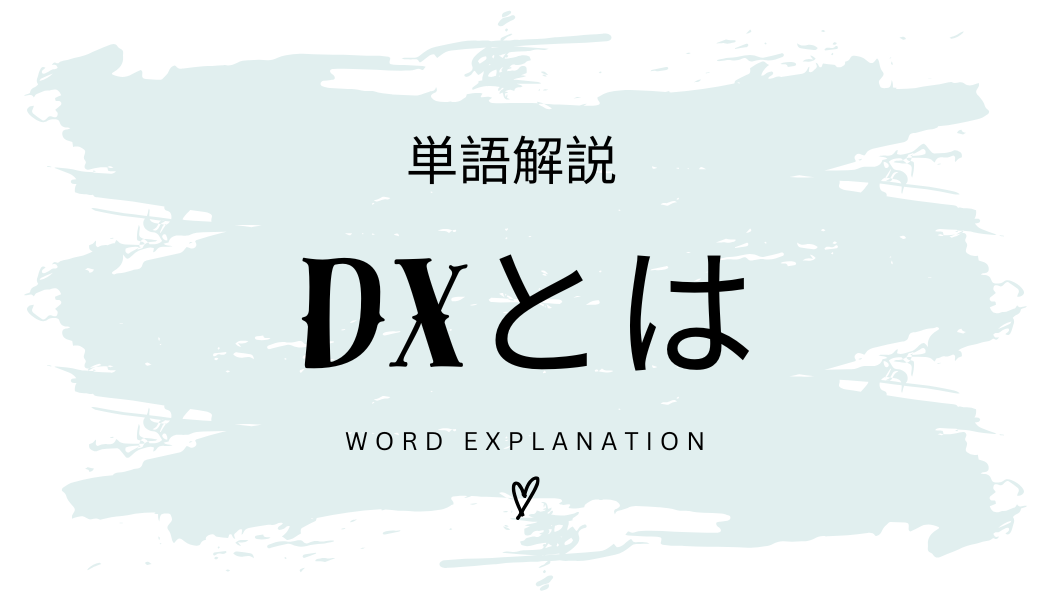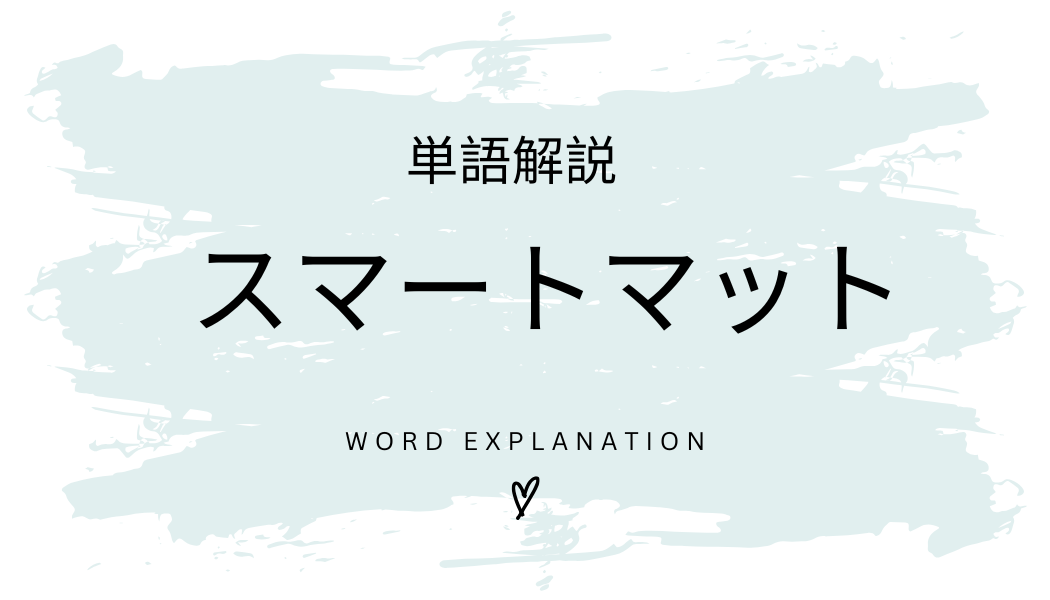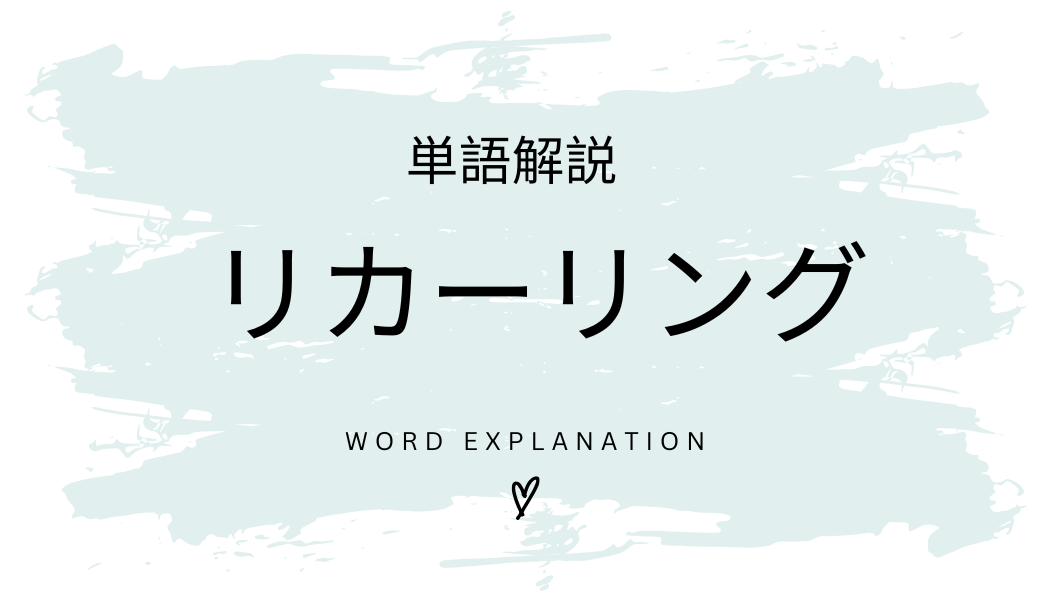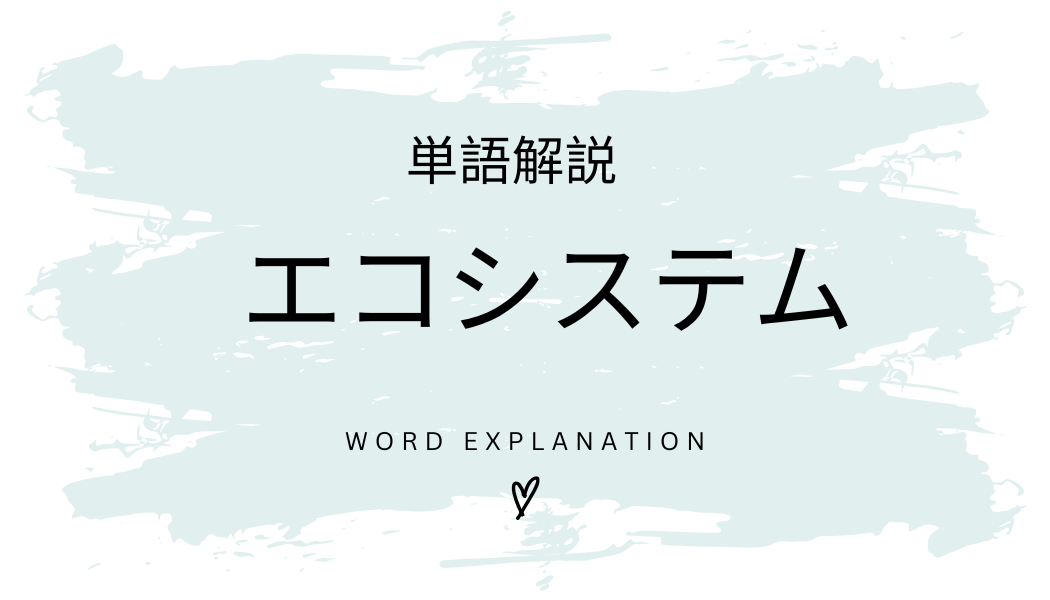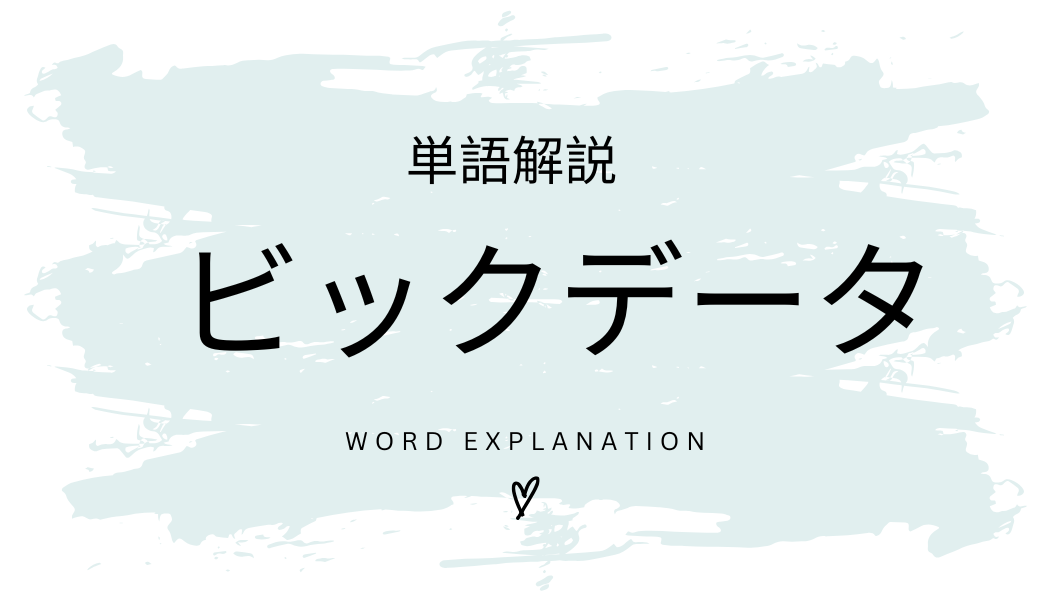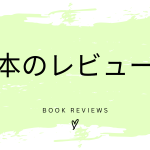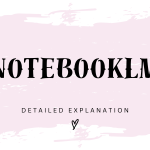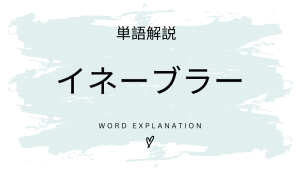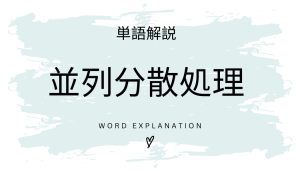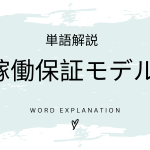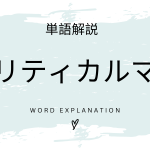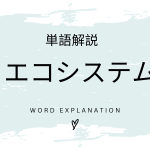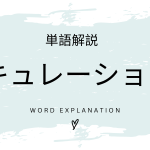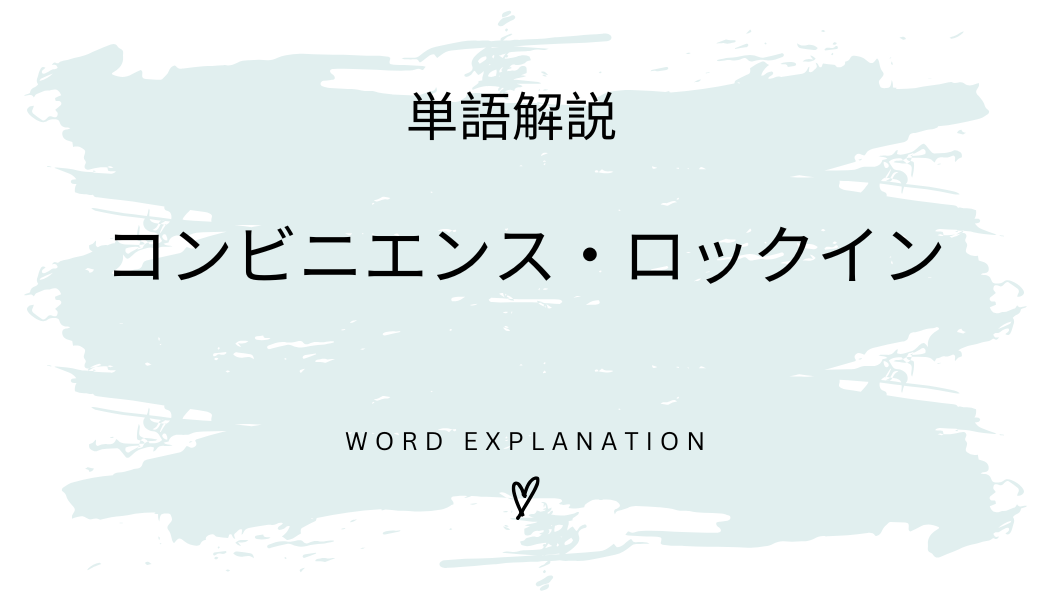
コンビニエンス・ロックインとは?IT初心者にもわかる!対話形式で学ぶDX時代の落とし穴

DXママ
「コンビニエンス・ロックイン」って言葉、聞いたことある?

あいちゃん
コンビニ...ロックイン?コンビニに閉じ込められるってこと?初めて聞いたよ!

DXママ
ふふ、文字通りの意味じゃないよ。「便利だから」という理由だけで特定のサービスやシステムに依存してしまい、抜け出せなくなる状態のことなんだ。「コンビニエンス(便利さ)」に「ロックイン(閉じ込められる)」されるってわけ。

あいちゃん
なるほど~!でも便利なものを使うのって悪いことなの?

DXママ
悪いことじゃないけど、短期的な便利さだけで選ぶと長期的に問題が出ることがあるんだ。例えば、無料で簡単に使えるクラウドサービスに大量のデータを入れたけど、あとから別のサービスに移行しようとしたら「データの移行に高額な費用がかかります」って言われたら困るでしょ?

あいちゃん
確かに!身動きが取れなくなっちゃうね。でも具体的にどんな例があるの?

DXママ
身近な例だと、特定のSNSで友達とやりとりするのが便利だからそのSNSをやめられなくなったり、特定のメーカーの製品を長く使っていて、他のメーカーに乗り換えるのが面倒になったりするのもコンビニエンス・ロックインの一種だよ。企業のITシステムだと、特定のベンダーの製品だけで構築してしまい、そのベンダーの言い値で契約せざるを得なくなる状況もあるんだ。

あいちゃん
なるほど~。DXを進める上でコンビニエンス・ロックインは問題なの?

DXママ
そうなんだ。DXの本質は「変化に柔軟に対応する力」を持つことでもあるんだけど、コンビニエンス・ロックインは選択肢を狭めて柔軟性を失わせるから、本当のDXの阻害要因になりかねないんだよ。「今は便利」だけでなく「将来の選択肢も確保できる」という視点で技術やサービスを選ぶことが大切なんだ。

あいちゃん
じゃあ、コンビニエンス・ロックインを避けるにはどうしたらいいの?

DXママ
いい質問!まずは、導入前に「このサービスやシステムを止めたくなったとき、どれくらい簡単に移行できるか」を考えることが大事。オープンな標準規格や互換性のあるシステムを選んだり、一つのベンダーに依存しすぎない「マルチベンダー戦略」を取ったりするのも有効だよ。それから、契約内容をしっかり確認して、データの所有権や移行条件を明確にしておくことも重要なんだ。
コンビニエンス・ロックインの基礎知識まとめ
コンビニエンス・ロックインについて、以下のポイントを押さえておきましょう:
- 定義:「便利だから」という理由だけで特定のサービスやシステム、ベンダーに依存してしまい、後から変更や移行が困難になる状態。
- 特徴:
- 短期的な利便性を優先して長期的なリスクを見落としがち
- 選択の自由が徐々に狭まっていく
- 移行コストや切替コストが高くなる
- 「慣れ」が変化への抵抗感を生み出す
- 気づいたときには既に深く依存してしまっていることが多い
- 具体例:
- 特定クラウドベンダーのサービスに全面的に依存し、独自APIやツールに縛られる
- 特定のSNSプラットフォームに顧客接点を集中させ、そのプラットフォームの方針変更に左右される
- 特定メーカーのエコシステム(例:スマートフォン、PC、周辺機器など)に依存する
- サブスクリプションサービスに依存し、価格が上がっても継続せざるを得ない状況
- レガシーシステムを「使い慣れているから」という理由だけで維持し続ける
- ビジネスへの影響:
- 価格交渉力の低下(ベンダーの言い値になりやすい)
- 柔軟性の喪失(市場変化に迅速に対応できない)
- イノベーション阻害(新技術やサービスへの移行が困難)
- コスト増大(長期的に見ると割高になることが多い)
- リスク集中(特定ベンダーの問題が自社の致命的問題になりうる)
- DXとの関連性:
- DXの本質は「変化への適応力」だが、コンビニエンス・ロックインはそれを阻害する
- 「とりあえずデジタル化」という表面的なDXは、新たなロックインを生み出す危険性がある
- 真のDXは、ロックインを避け持続的な変革を可能にする基盤を作ること
- 防止策・対策:
- マルチベンダー戦略:複数のベンダーやサービスを組み合わせる
- 標準規格の重視:オープンスタンダードや業界標準に準拠したシステムを選ぶ
- 出口戦略の明確化:導入前に「やめる時」のシナリオを検討する
- データポータビリティの確保:自社データの所有権と移行可能性を担保する
- 契約条件の精査:ロックイン要素がないか契約内容を慎重に確認する
- 定期的な見直し:使用中のサービスやシステムを定期的に評価し直す
- コスト以外の評価軸:短期的な便利さや価格だけでなく、長期的な価値や柔軟性も評価する
コンビニエンス・ロックインは、デジタル時代において特に注意すべき落とし穴です。便利さという誘惑に負けず、長期的な視点での選択を心がけることが、持続可能なDX推進には欠かせません。「今日の便利さ」と「明日の自由度」のバランスを常に意識し、柔軟性を保持したデジタル戦略を構築していきましょう。