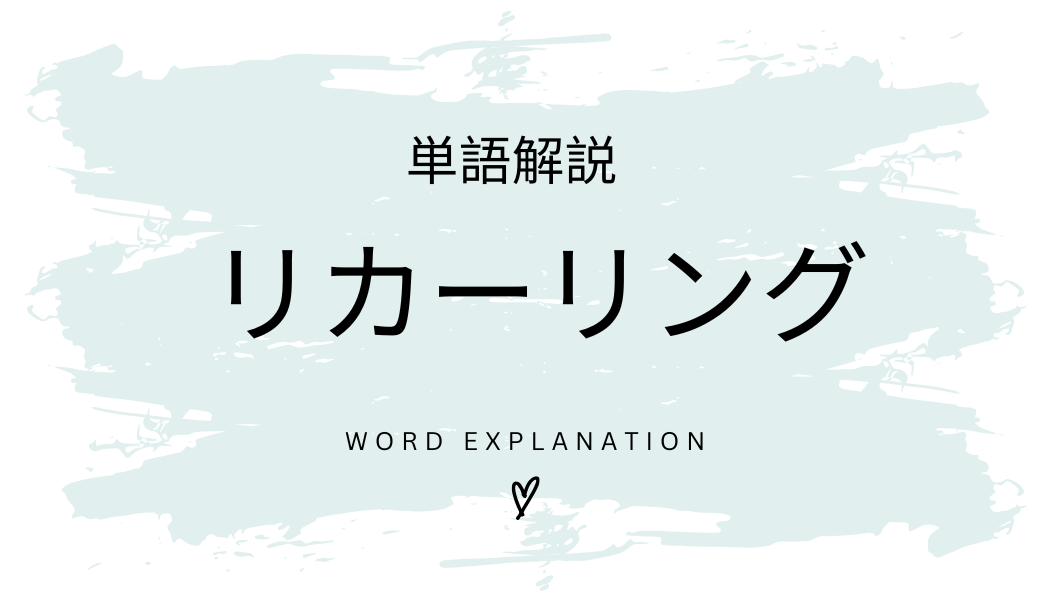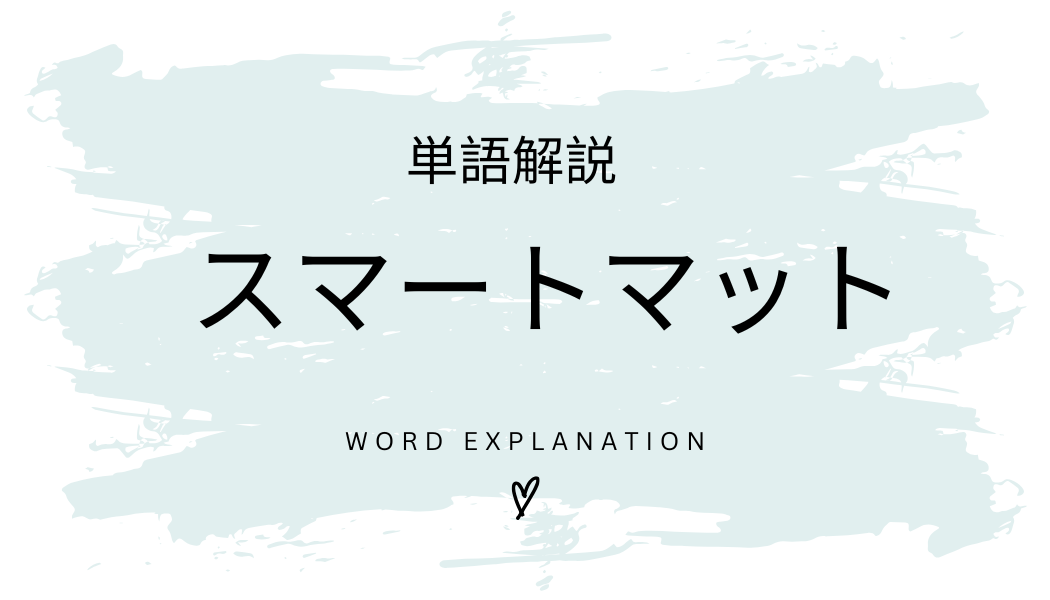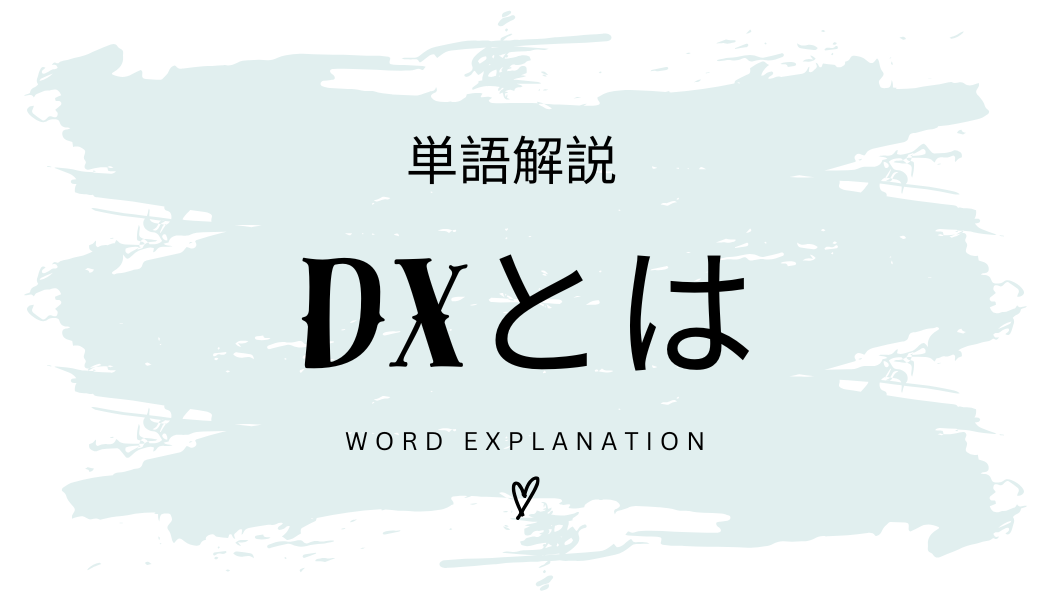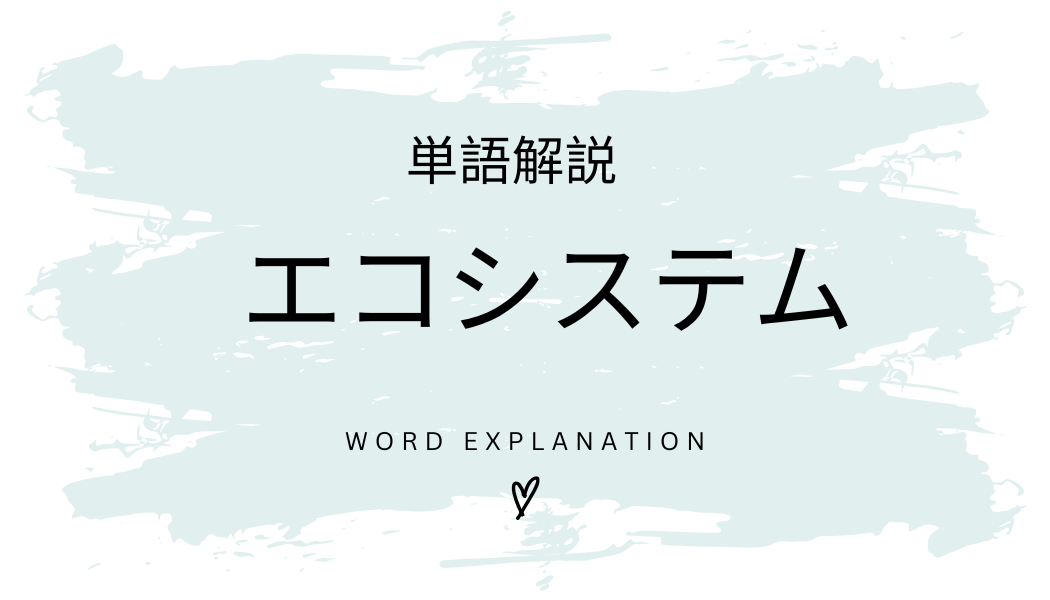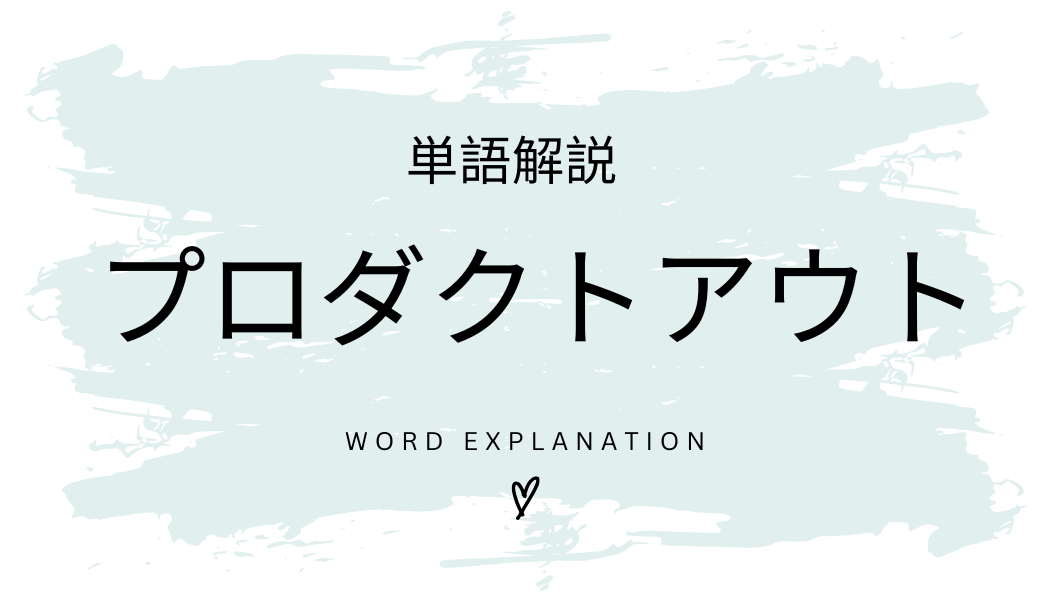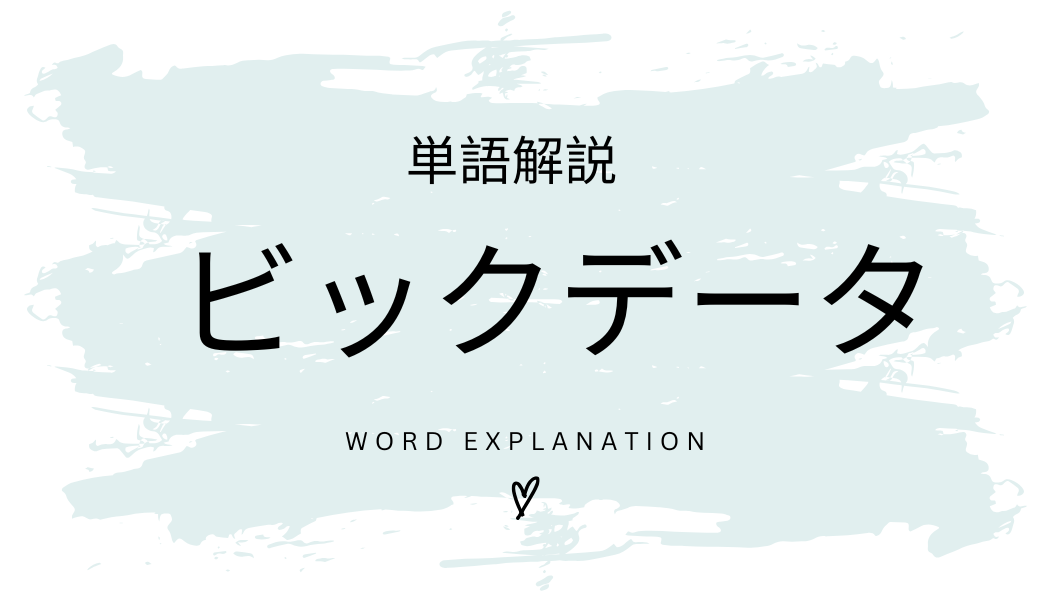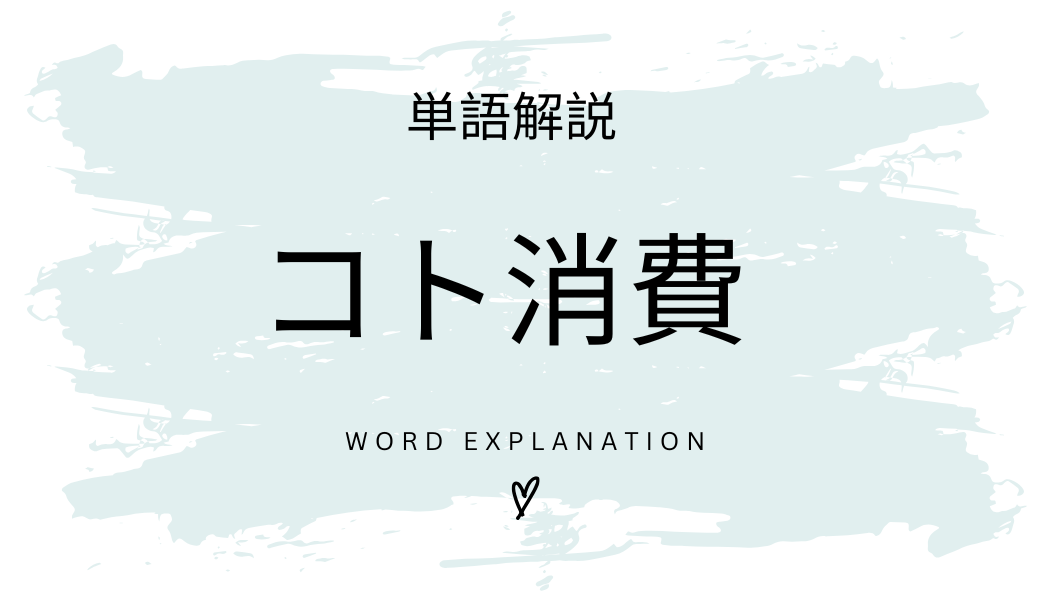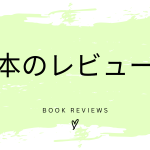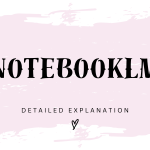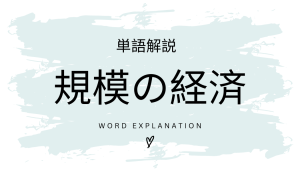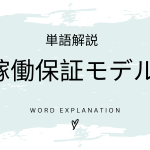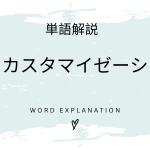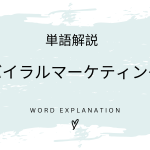DXママ
あいちゃん、最近「コト消費」って言葉をよく聞くけど知ってる?

あいちゃん
コト消費?なんか聞いたことはあるけど、よくわかんない。普通の買い物と何が違うの?

DXママ
簡単に言うと、物を買うんじゃなくて「経験」や「体験」にお金を使うことよ。例えば、高い服を買うよりもライブに行ったり、おいしいレストランで食事したり、旅行に行ったりすることにお金を使う消費スタイルのことなの。「モノ消費」と対比して「コト消費」って言われてるのよ。

あいちゃん
なるほど!確かに私も友達と映画見に行ったり、カフェでおしゃべりしたりするの好きだし。でも、なんで最近そんな風に変わってきたの?

DXママ
いくつか理由があるのよ。まず、日本はすでにモノが溢れてて、単に持ち物を増やすことに満足感が得られにくくなってきたの。それにSNSの普及で、「私、こんな素敵な経験をしたよ!」って共有することに価値を感じる人が増えたのね。あとは価値観の変化で、「所有すること」より「体験すること」に幸福を感じる人が増えてきたってことかな。

あいちゃん
確かに!物よりも思い出の方が大事だよね。でも、これってDXとも関係あるの?

DXママ
もちろんよ!デジタル技術の発展は「コト消費」の広がりと深く関係してるの。例えば、スマホのARを使った観光アプリ、VRで体験できる新しいエンターテイメント、オンラインでのライブ配信、デジタル技術を活用した体験型ミュージアムなど、テクノロジーの進化でこれまでにない「コト消費」が生まれてるわ。企業もただ商品を売るだけじゃなく、どんな体験を提供できるかを考えるようになってるの。

あいちゃん
へー!確かにインスタ映えするカフェとか、VRアトラクションとか増えてきたよね。私も写真撮れる場所やイベントに行きたくなるし、そういうのが「コト消費」なんだね!
コト消費とは:まとめ
コト消費とは、物品(モノ)の購入ではなく、サービスや体験などの「経験」にお金を使う消費行動のことです。従来の「モノ消費」と対比される概念で、近年の消費トレンドとして注目されています。
- コト消費の定義と特徴:
- 物品の「所有」ではなく、サービスや体験の「経験」に価値を見出す消費行動
- 一時的な体験であっても、記憶や思い出として残り続ける価値を重視
- SNSなどで共有できる経験や体験が特に人気(インスタ映えする体験など)
- 個人の趣味や嗜好に合わせたパーソナライズされた体験への需要が高い
- コト消費の例:
- 旅行・観光体験(テーマパーク、体験型観光など)
- エンターテイメント(ライブ、コンサート、スポーツ観戦など)
- 体験型ワークショップ(料理教室、DIY体験、クラフト体験など)
- 飲食体験(特別なレストラン、食べ歩きなど)
- 美容・健康サービス(エステ、スパ、フィットネスなど)
- 学習・自己啓発(セミナー、オンライン講座など)
- コト消費が広がった背景:
- モノの飽和:すでに物が溢れている社会での消費の変化
- 価値観の変化:所有より体験に幸福を感じる傾向の増加
- SNSの普及:体験を共有することの価値の向上
- ミレニアル世代・Z世代の台頭:若年層のライフスタイル志向の強まり
- 環境意識の高まり:モノを持ちすぎないサステナブルな生活志向
- DX(デジタルトランスフォーメーション)との関係:
- AR/VR技術による新しい体験型コンテンツの創出
- スマートフォンアプリを活用した体験拡張(観光ガイドアプリなど)
- オンラインプラットフォームによる体験予約・シェアの容易化
- デジタル技術を活用した体験型店舗・施設の増加
- パーソナライズされた体験提供のためのデータ活用
- ビジネスへの影響:
- 製品中心から顧客体験(CX)中心のビジネスモデルへの転換
- 体験を提供するサブスクリプションモデルの普及
- 小売店の「体験の場」としての再定義(ショールーミング)
- オンラインとオフラインを融合した体験設計(OMO:Online Merges with Offline)
- 顧客との長期的な関係構築を促進するエンゲージメント戦略の重要性
DX時代において、コト消費は単なるトレンドを超え、ビジネスモデルの変革を促す重要な概念となっています。企業は製品やサービスを通じて「どのような体験を提供できるか」を考え、顧客との関係構築を重視したアプローチが求められています。また、デジタル技術の進化によって、これまでにない新しい体験の創出が可能になり、コト消費の可能性はさらに広がっていくでしょう。