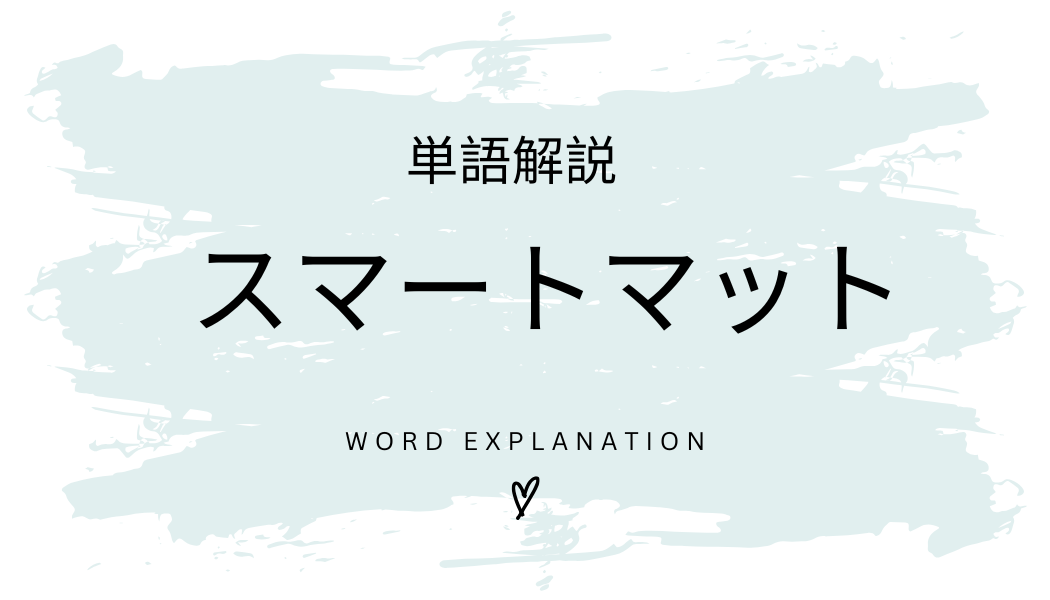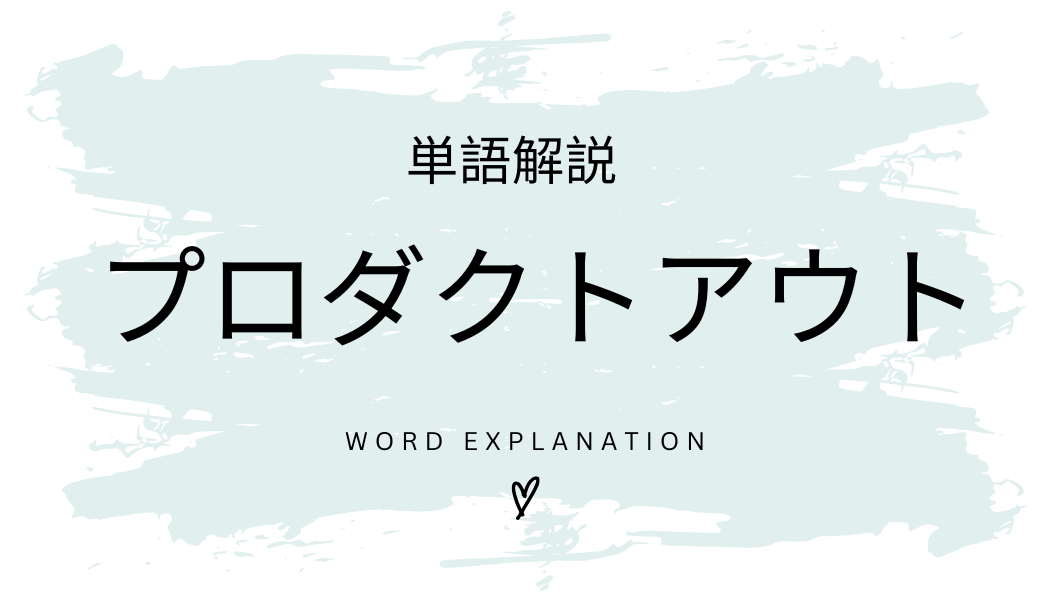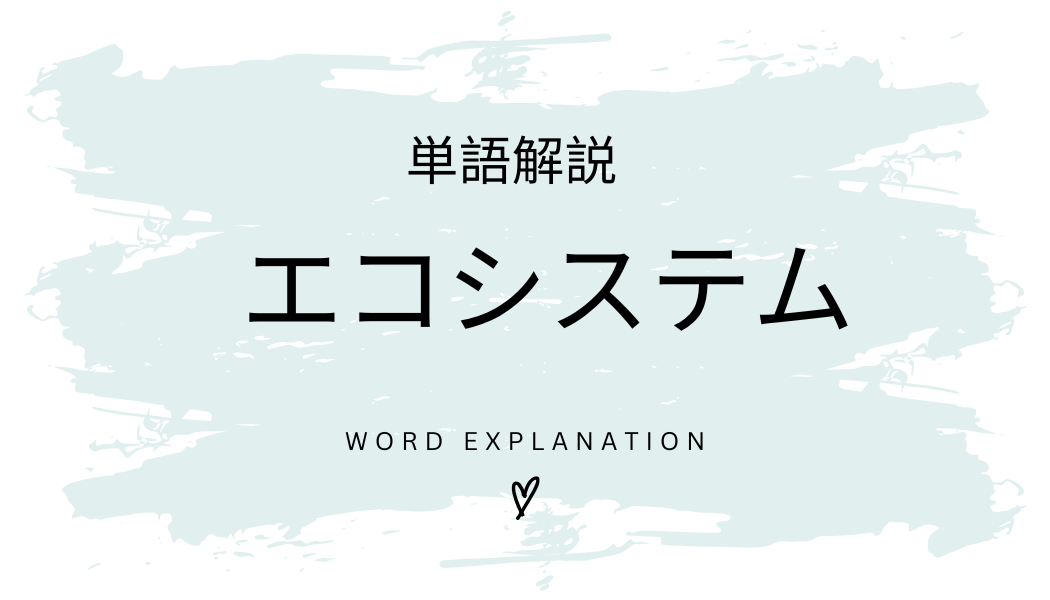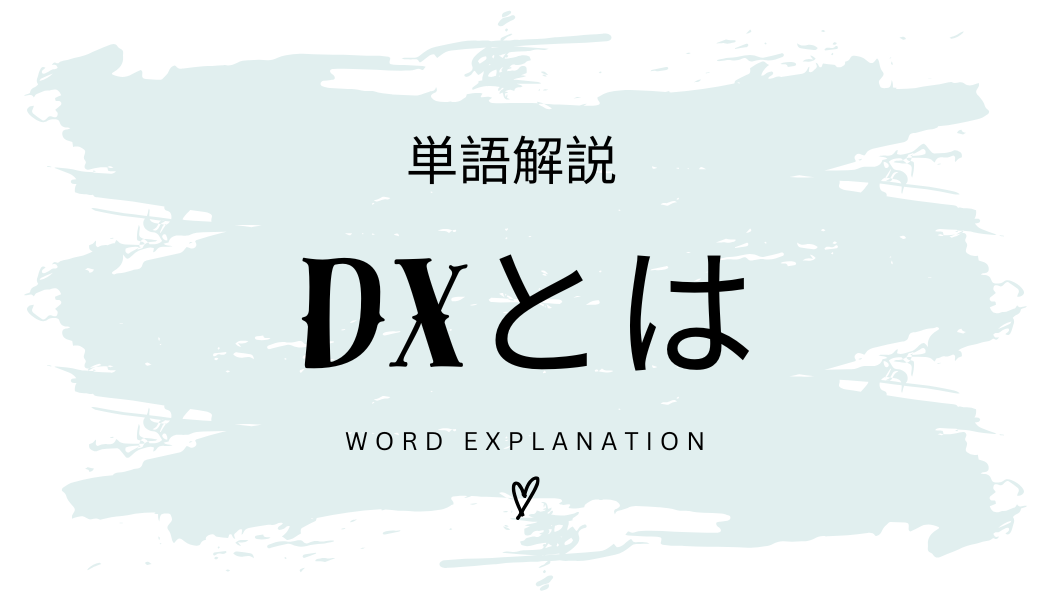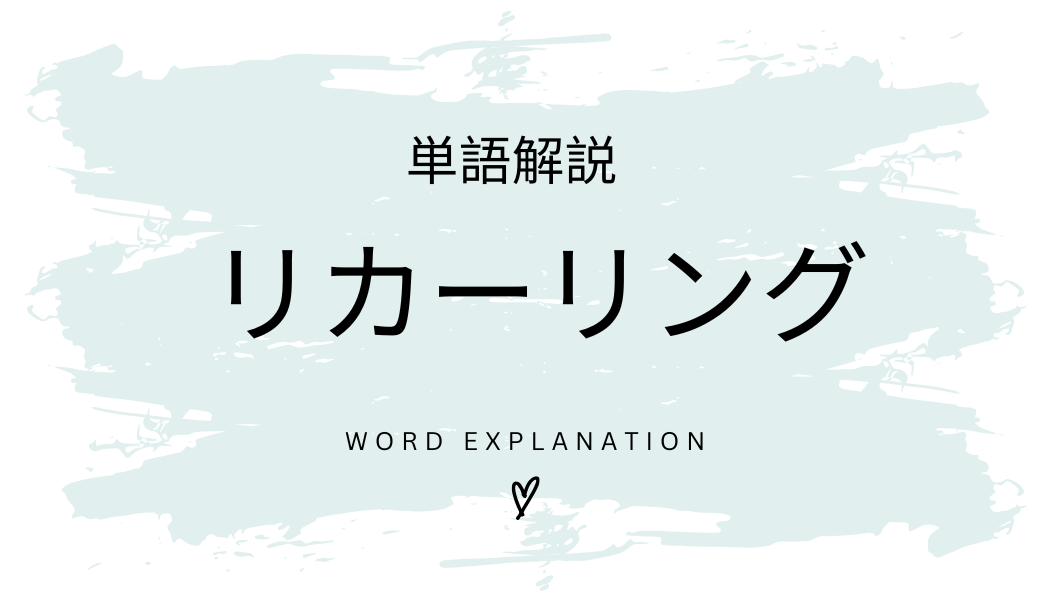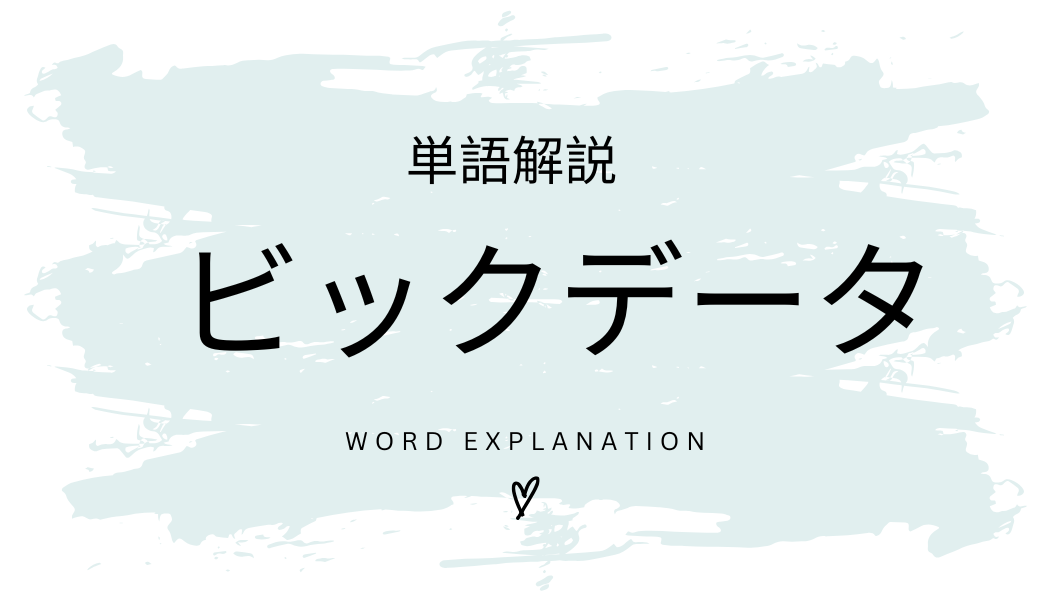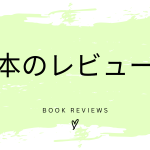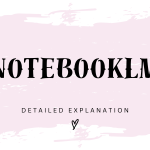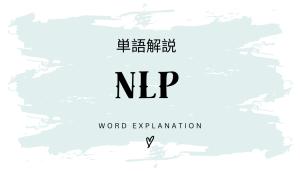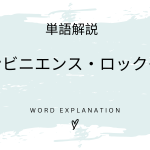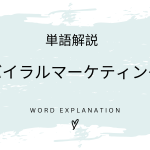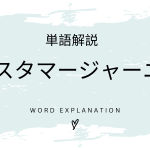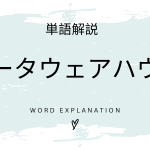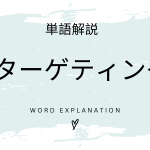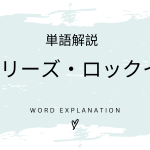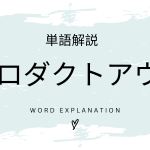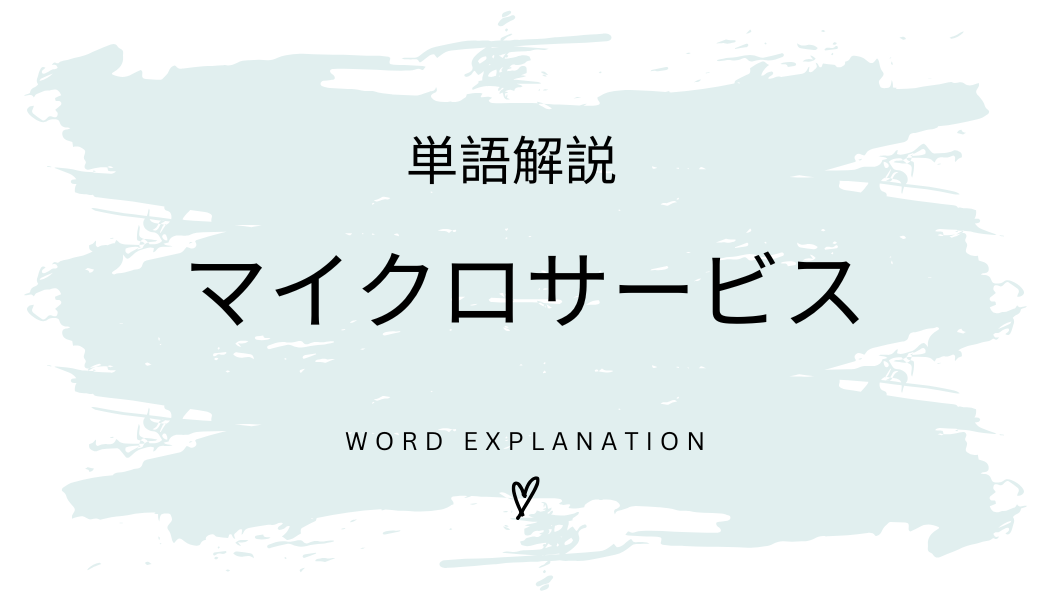
マイクロサービスとは?小さく分けて強くするシステム開発手法をわかりやすく解説

DXママ
あいちゃん、最近の会社でよく聞く「マイクロサービス」って言葉知ってる?IT部門の人たちがよく使ってるんだけど。

あいちゃん
ううん、全然知らない!なんか小さなサービスってこと?お店の小さいサービスとか?

DXママ
そうじゃなくて、コンピューターのシステムを作る方法の一つなんだよ。簡単に言うと、大きな一つのシステムを作るんじゃなくて、小さな部品みたいなサービスに分けて作るっていう考え方なんだ。例えるなら、レゴブロックみたいに小さな部品を組み合わせてシステムを作るイメージかな。

あいちゃん
レゴブロックみたいに?でも、どうして大きな一つじゃなくて小さく分けるの?

DXママ
いい質問だね!例えばネットショップのシステムを考えてみようか。従来のやり方(モノリシックって言うんだけど)だと、商品表示、検索、カート、決済、配送管理など全部が一つの大きなシステムになってるの。これだと一カ所変更するだけでも全体をテストし直さないといけないし、機能追加も大変なんだ。

あいちゃん
なるほど!大きな一つだと変更が難しそう。マイクロサービスだとどうなるの?

DXママ
マイクロサービスだと、商品表示サービス、検索サービス、カートサービス、決済サービス、配送管理サービスなど、機能ごとに独立した小さなシステムに分けるの。それぞれが独立してるから、決済サービスだけ変更したい時は、そこだけ触ればいいし、商品検索を強化したい時も、検索サービスだけ強化すればいいんだ。

あいちゃん
それって便利そう!でも小さく分かれてると、お互いどうやって連携するの?バラバラになっちゃわない?

DXママ
その疑問もすごく大事!連携はAPIって仕組みを使うんだ。APIは「アプリケーション・プログラミング・インターフェース」の略で、サービス同士が会話する共通言語みたいなものなの。例えば、カートサービスが「この商品の在庫確認して」って商品サービスにお願いするとき、APIを通して話すんだ。それぞれのサービスは独立しつつも、APIを通じて必要な情報をやりとりできるようになってるよ。

あいちゃん
なるほど!独立してるけど会話はできるんだね。でもマイクロサービスって全部いいことばかりなの?何か難しいところはないの?

DXママ
さすがあいちゃん、鋭いね!もちろん課題もあるよ。まず複雑さが増すんだ。たくさんの小さなサービスを管理するのは、一つの大きなシステムを管理するより難しいことがあるの。あと、サービス間の通信が増えるから、全体のパフォーマンスが落ちることもあるし、サービス同士の依存関係を正しく設計しないと、問題が起きたときの切り分けが難しくなることもあるんだ。単純なシステムなら、むしろ一つの大きなシステムの方が適していることも多いよ。
マイクロサービスとは?まとめ
マイクロサービスは、大きな一つのシステム(モノリシック)ではなく、機能ごとに独立した小さなサービスに分割してシステムを構築する開発手法です。それぞれのサービスは独自のデータベースを持ち、APIを通じて他のサービスと連携します。以下にポイントをまとめます:
- マイクロサービスの基本概念:
- 機能ごとに小さく分割された独立したサービス群でシステムを構成
- 各サービスは単一の責任を持ち、特定の業務機能に特化
- それぞれが独自のデータベースを持ち、独立してデプロイ可能
- APIを通じて他のサービスと通信・連携
- 従来のモノリシックアーキテクチャとの違い:
- モノリシック:すべての機能が一つの大きなシステムに統合されている
- マイクロサービス:機能ごとに分割され、独立して開発・展開が可能
- マイクロサービスのメリット:
- 柔軟性と拡張性:個別のサービスだけを独立して拡張・変更できる
- 技術の多様性:各サービスに最適な言語やデータベースを選択可能
- 障害の局所化:一部のサービスに問題が発生しても、全体が停止しにくい
- チーム編成の柔軟性:機能ごとに小さなチームで開発可能
- デプロイの迅速化:変更したサービスだけを素早くリリースできる
- マイクロサービスの課題:
- 複雑性の増加:多数のサービスを管理する難しさ
- 分散トランザクション:複数のサービスにまたがる処理の整合性確保が難しい
- ネットワークオーバーヘッド:サービス間通信による遅延
- 運用の複雑さ:モニタリングやデバッグが複雑になる
- 適切な境界設計の難しさ:サービスの責任範囲をどう区切るかが重要
- 関連技術とツール:
- コンテナ技術(Docker、Kubernetes):サービスの独立した実行環境
- API管理:RESTful API、GraphQL、gRPCなど
- サービスメッシュ:サービス間通信の管理(Istio、Linkerd)
- CI/CD:継続的インテグレーション/デリバリーツール
- モニタリング:分散トレーシングやログ集約ツール
- 主な活用例:
- Amazon、Netflix、Uber、Spotifyなどの大規模Webサービス
- 頻繁な機能追加や変更が必要なECサイト
- 異なるチャネル(Web、モバイル、IoTなど)に対応する必要のあるシステム
マイクロサービスアーキテクチャは、すべてのシステムに適しているわけではありません。システムの規模、チームの体制、ビジネスの要件などを考慮して、適切なアーキテクチャを選択することが重要です。小規模なシステムや、頻繁な変更が不要なシステムでは、従来のモノリシックアーキテクチャの方がシンプルで管理しやすい場合もあります。