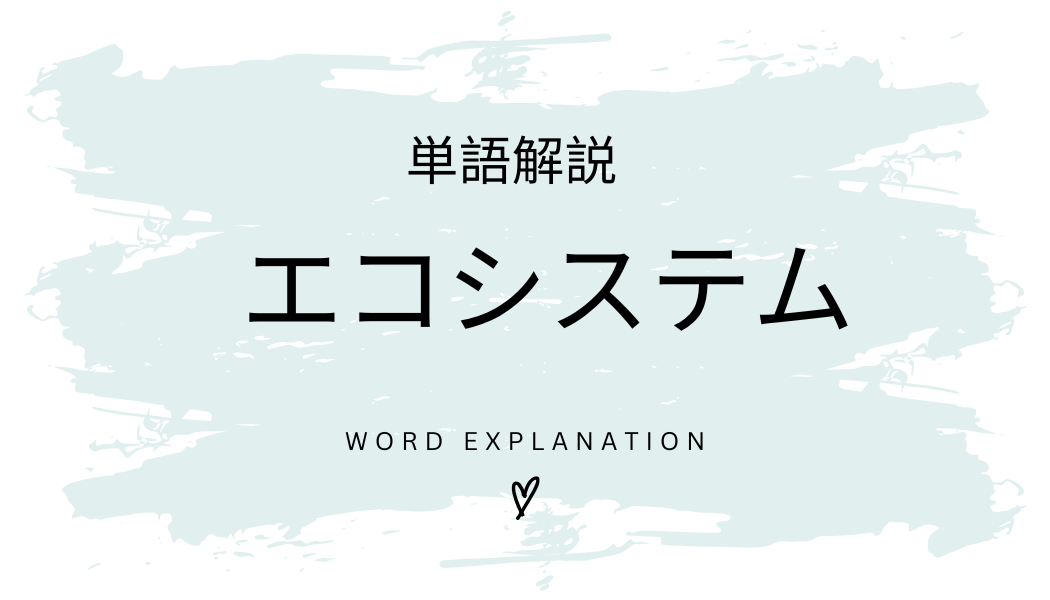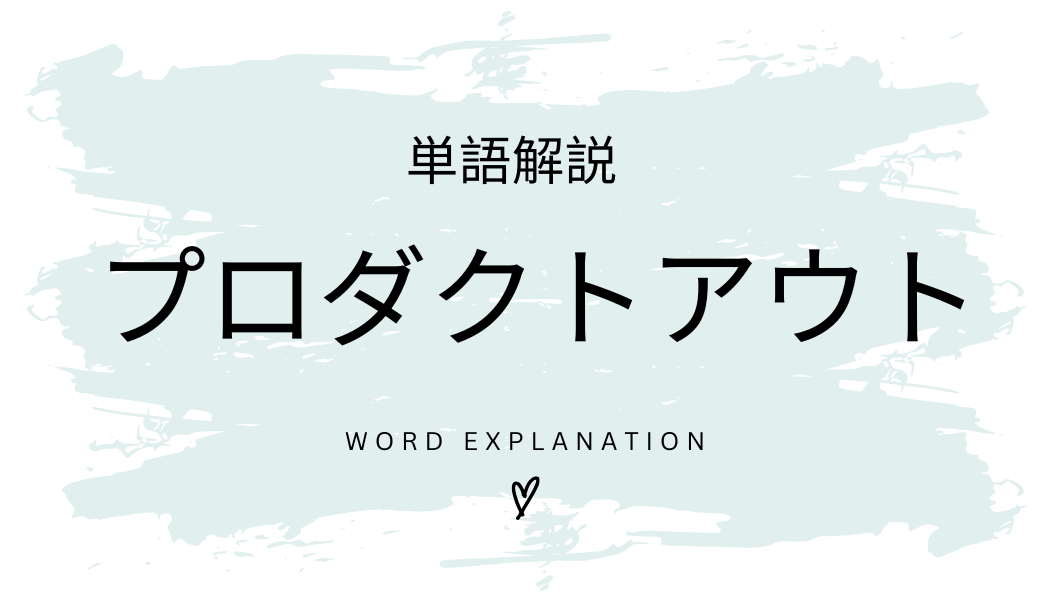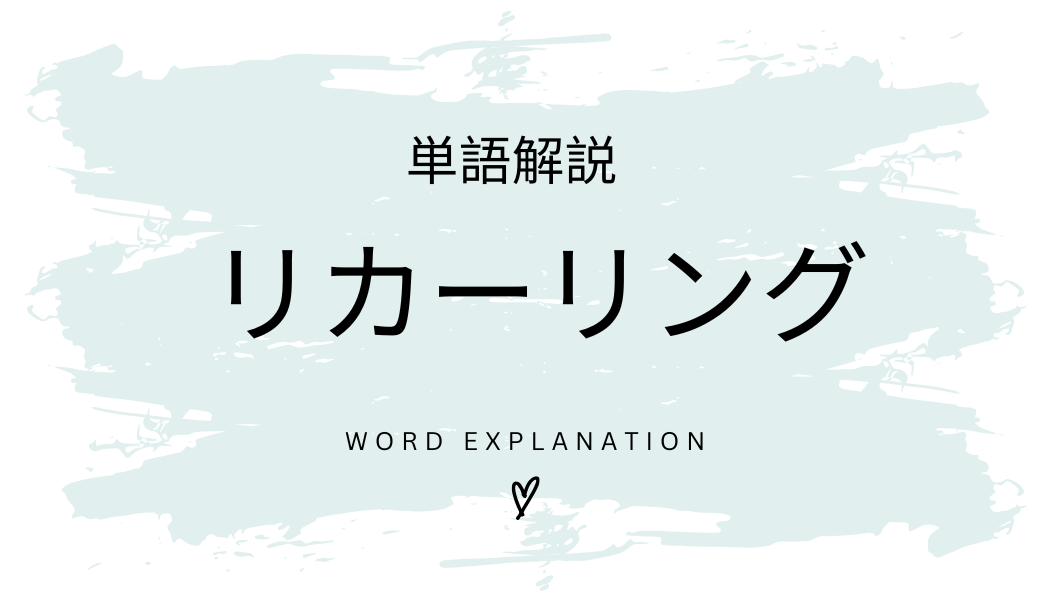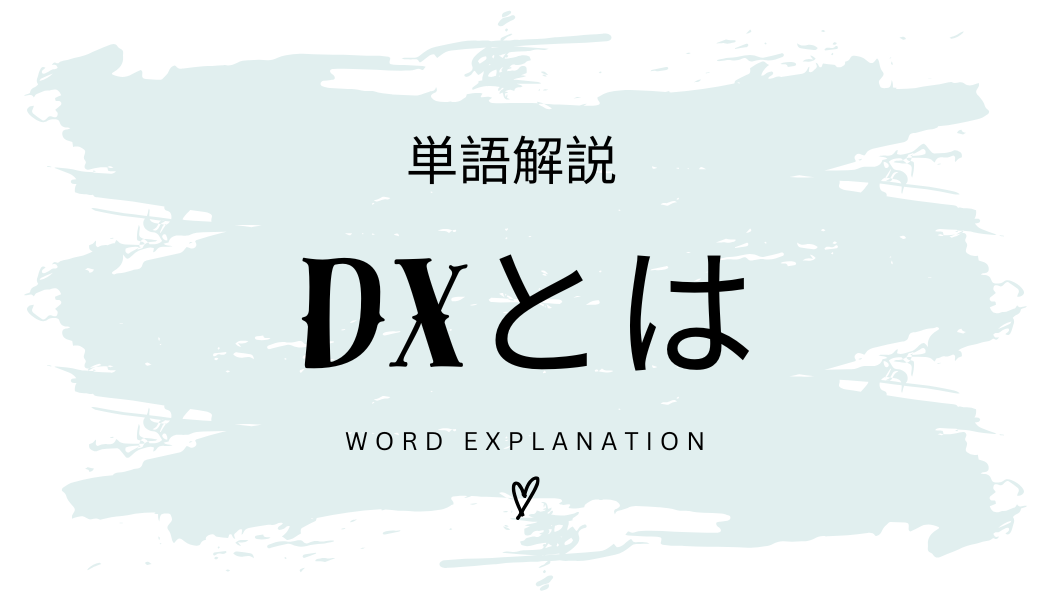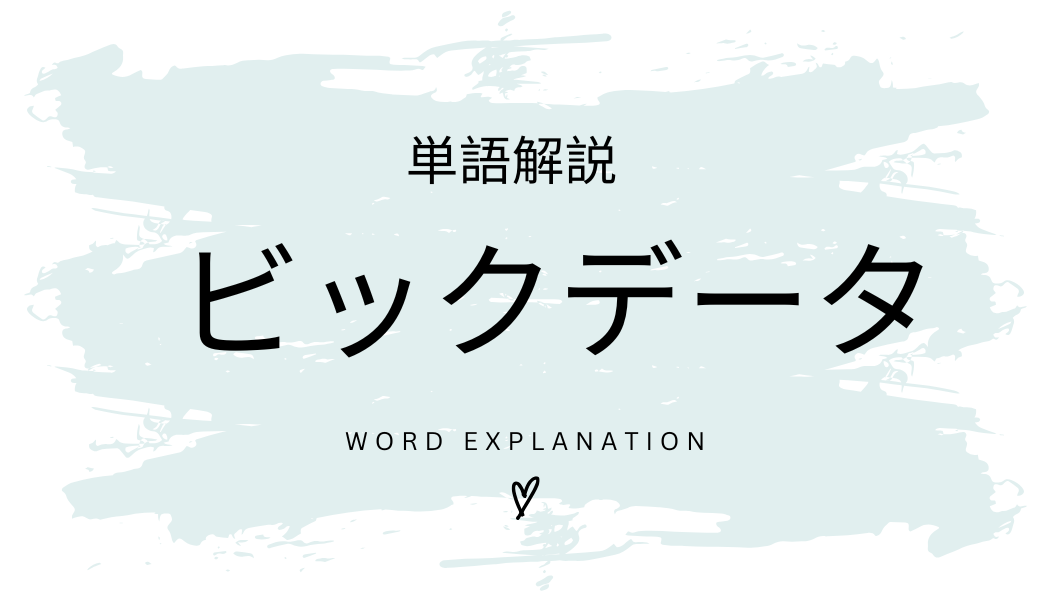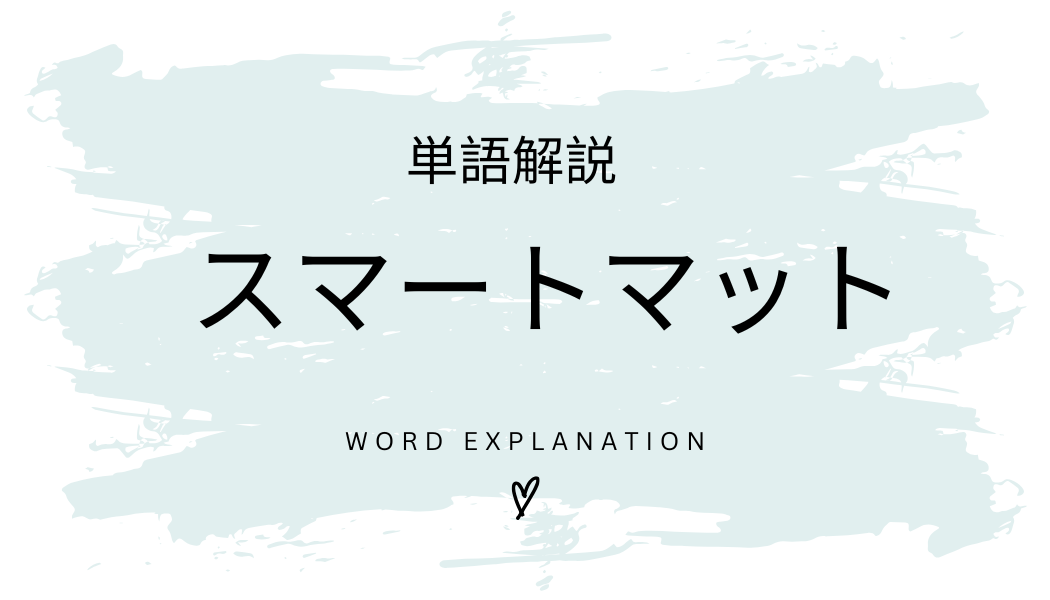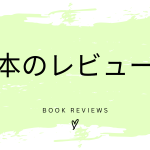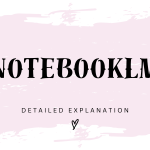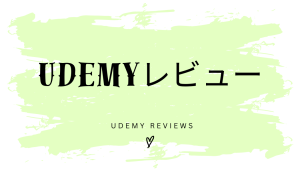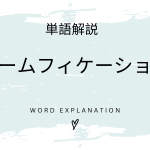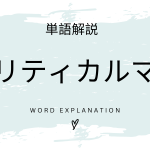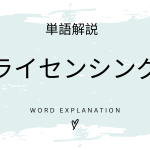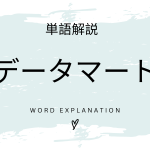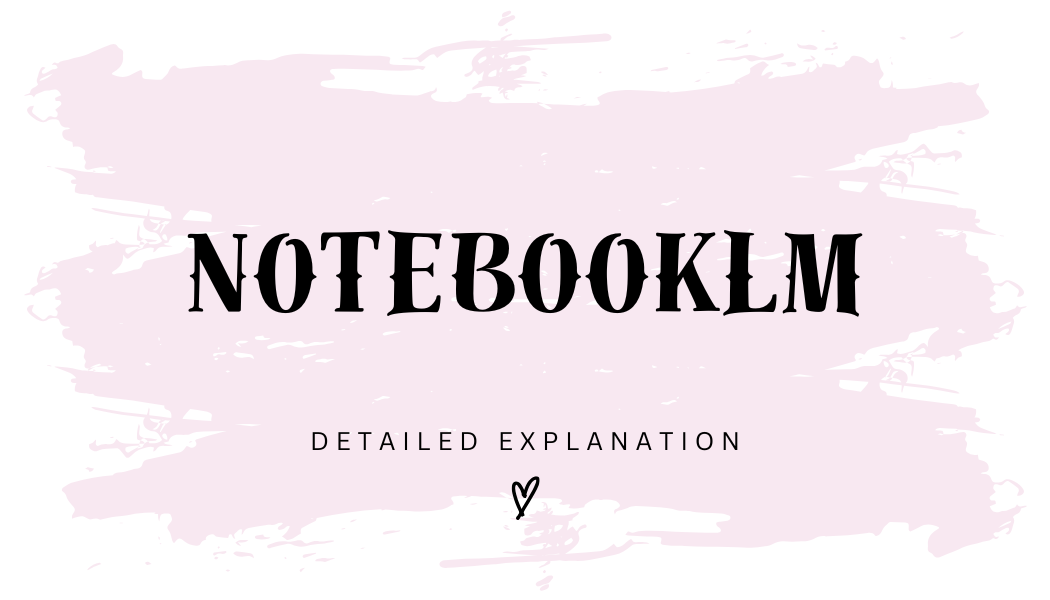



NotebookLMとは?なぜ今、注目されているのか
NotebookLMは、Googleが開発したAI搭載のノートツールです。AI界隈では「最もお勧めできるAIツール」の一つとして非常に高い評価を受けてます。
私も大好きなツールです。簡単で使いやすくて、活用シーンも多いです!
実は、会社のDX共有会で発表したことがあります。
一般的な生成AI(ChatGPTなど)が大量の学習データからテキストを生成するのに対し、NotebookLMの最大の特徴は、ユーザーがアップロードした情報のみを「ソース」としてAIが分析し、回答を生成する点にあります。この「ソース設置型」のアプローチにより、情報の正確性や信頼性が格段に高まります。
NotebookLMの主なメリット:
- ハルシネーション(AIがもっともらしい嘘をつく現象)のリスクが少ない:ユーザーが追加した情報のみを参照するため、事実と異なる情報を生成するリスクが抑えられます。
- 回答の出典が明確:生成された回答には必ず参照元が表示され、どの資料のどの部分から情報が引用されたかを確認できます。これにより、情報の正確性を容易に検証できます。
- 無料から利用可能:個人ユーザーは無料で利用でき、Googleアカウントがあればすぐに始めることができます。より高度な利用や組織での利用には有料の「NotebookLM Plus」プランも用意されており、Google One AIプレミアムプラン加入者などは追加料金なしで利用可能です。
NotebookLMのAIエンジンには、Googleの大規模言語モデルであるGeminiが活用されています。
NotebookLMの驚くべき機能
NotebookLMは、単に質問に答えるだけでなく、情報を整理し、理解を深めるための多彩な機能を備えています。
主要機能一覧
- ソースの追加方法: PDF、テキスト、マークダウンファイル、Googleドライブのドキュメントやスライド、ウェブサイトのリンク、そしてYouTube動画のリンク(文字起こし情報を読み込みます)など、多様な形式の情報をソースとして追加できます。ログインが必要なクローズドな情報やSNSの投稿などは、直接テキストを貼り付けることも可能です。
- メモ機能: AIの回答や自分で考えたことをメモとして保存でき、これらのメモを新たなソースとして活用することも可能です。
- マインドマップ: アップロードした資料の内容を視覚的に分かりやすいマインドマップに変換します。各要素をクリックすると、チャット欄で詳細な解説を得られます。
- よくある質問: 資料に基づいて、ユーザーが抱きそうな質問と回答を自動生成し、資料の理解を深めるヒントを提供します。
- 学習ガイド: 資料の内容に基づいて、小テストや用語集を自動的に作成します。知識の定着度を確認したり、専門用語を効率的に習得するのに役立ちます。
- ブリーフィングドキュメント: ソースの情報を要約し、概要をまとめたドキュメントを作成します。ノート全体の全体像を素早く把握するのに便利です。
- 共有機能: 作成したノートブックを他のユーザーと共有できます。チームでの共同作業や情報共有がスムーズに行えます。有料プランでは、チャット部分のみを共有する機能もあります。
- アナリティクス(Plusプラン限定): 共有されたノートブックの利用状況(ユーザー数、質問数など)を把握できます。チーム内での情報共有や共同作業の効率性を評価するのに役立ちます。
最新機能:動画概要(Video Overview)の追加!
NotebookLMの最新機能として「動画概要」が追加されました。これは、ノートブックに入力したソースを基に、ボタン一つで動画解説資料を作成してくれる画期的な機能です。
残念ながら、現時点では英語での生成のみに対応していますが、近い将来日本語にも対応することが期待されています。
私は、運よく日本語の動画が作れました。
これは、東京大学 松尾・岩澤研究室が作成したLLM(大規模言語モデル)大規模言語モデル講座の講義資料です。NotobookLMに入れて、動画を作ってもらいました。
資料が膨大すぎるので、かなり概要だけになっていますが、動画の質はなかなかです。
この機能は、YouTubeなどの解説動画市場にも大きな影響を与える可能性を秘めています。
GemsとNotebookLM:あなたに最適なのはどちら?
NotebookLMと並んでGoogleが提供するAIツールに「Gems」があります。どちらも独自の知識を追加できる点で共通していますが、その目的と機能には明確な違いがあります。これらを理解することで、自身のニーズに合わせた最適なツールを選ぶことができます。
| 特徴 | Gems | NotebookLM |
|---|---|---|
| 目的 | 資料を基に何ができるか(創造的アウトプット)を考える | 資料に何が書かれているかを正確に知る(厳密な分析) |
| 知識の扱い方 | 知識拡張型 (Geminiの広範な知識を基に拡張) | ソース設置型 (アップロードした資料のみを基に回答) |
| 最適な資料 | 製品カタログ、マーケティング資料、ブログ記事 (創造的利用) | 法律の条文、技術マニュアル、学術論文、会議録 (正確性が求められるもの) |
| 期待する回答 | 創造的、主観的な提案や生成物 | 記述に忠実で、出典が明確な情報 |
| 主な得意分野 | アイデア出し、ブレインストーミング、企画立案 | ファクトチェック、厳密な分析、議事録作成、マニュアル理解 |
| 主な制限 | 情報の正確性や出典特定が難しい傾向、チーム共有機能なし(Googleアプリ連携はあり) | 発想の広がりが少ない |
| ソース上限 | 最大10個 | 無料版50件、有料版300件 |
| Googleアプリ連携 | Gmail, ドキュメント, スプレッドシート, ドライブのパネル内で利用可能 | なし |
Gemsは、Geminiの広範な知識や創造性を、与えられた資料を「土台」としてさらに引き出すことを目的としています。例えば、製品カタログを基に新しいキャッチコピーを考案したり、既存のガイドラインを守りながら新しいロゴのアイデアをスケッチしたりするなど、創造的なアウトプットに優れています。
一方、NotebookLMは、ユーザーがアップロードした資料の「内容を正確に、忠実に理解し、整理する」ことに特化しています。法律の条文や技術マニュアル、会議録など、一語一句の正確性が求められる資料に適しており、資料に書かれていないことは基本的に回答しません。
つまり、特定の知識をベースにした創造的な作業やブレインストーミングを行いたい場合はGemsを、ファクトチェックや厳密な分析が最優先される場合はNotebookLMを選ぶのが最適です。
日常からビジネスまで広がる活用シーン
NotebookLMは、その高い情報整理能力と信頼性から、多岐にわたる活用が可能です。
日常や個人での活用例:
- YouTube動画の効率的な視聴: 動画のURLをソースに入れ、要点を抽出したり、マインドマップを作成したりすることで、長時間の動画から必要な情報を素早く把握できます。
- 難しい情報の理解: 論文や外国語の資料を読み込ませ、分かりやすく解説してもらうことができます。
- 自分だけの学習教材の作成: 動画や記事、教材を読み込ませ、テスト問題や用語集を作成することで、効率的な学習と復習が可能です。
- 旅行プランの計画: 候補地の情報や記事を読み込ませて比較・整理することで、自分好みの旅行計画を即座に作成できます。
ビジネスでの活用例:
- 議事録の自動作成: 会議の録音や文字起こしデータをソースに入れ、要点や決定事項、未解決事項などをまとめさせることで、瞬時に議事録を作成できます。
- 商談や社内会議の振り返り: 過去の録音や文字起こし、議事録データをすべてソースに追加することで、商談の経緯を整理したり、担当者変更時の引き継ぎ資料を簡単に作成できます。
- 社内チャットボットの構築: 社内規定やマニュアルなどの資料を学習させ、従業員からの質問に自動で回答させることで、質問対応の負荷を軽減し、業務に集中できる環境を整えます。
また、NotebookLMは、ChatGPTやGeminiなどの検索AIや、Gamma AIなどのスライド生成AIと組み合わせることで、情報収集、プレゼン資料作成、記事・動画台本作成などの効率を飛躍的に向上させることも可能です。
利用上の留意点
NotebookLMを利用するにあたり、いくつかの重要な留意点があります。
- データとプライバシー: Googleは、アップロードされた資料や会話履歴がAIの学習データに使われないと公式に表明しています。ただし、フィードバックを送信した場合は、人間が内容を確認する可能性があるため、共有したくない情報は送信しないことが推奨されます。
- 回答の信頼性: ハルシネーションのリスクは低いものの、資料が不完全であったり、高度な専門分野(医療、法律、財務など)では誤った内容を返す可能性もあります。専門的なアドバイスが必要な場合は、必ず専門家の確認が必要です。
- チーム共有時の権限設定: チームで利用する際は、閲覧者、編集者、チャットのみ(Plusプラン限定)など、適切なアクセス権限を設定することが重要です。
まとめ
NotebookLMは、あなたが持つ情報を正確に理解し、整理し、新たな価値を生み出すための強力なAIツールです。個人利用からビジネスでのチーム活用まで、幅広いシーンであなたの生産性を高めてくれますよ。
無料から手軽に始められるので、ぜひ一度体験してみてください。あなたの情報管理と業務のあり方が、きっと劇的に変わるはずです。