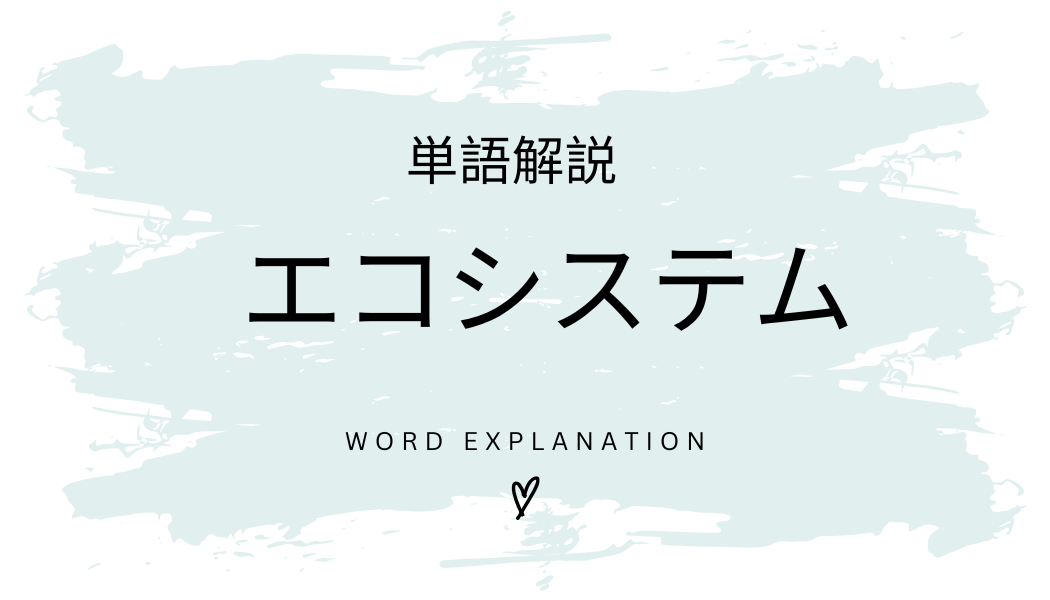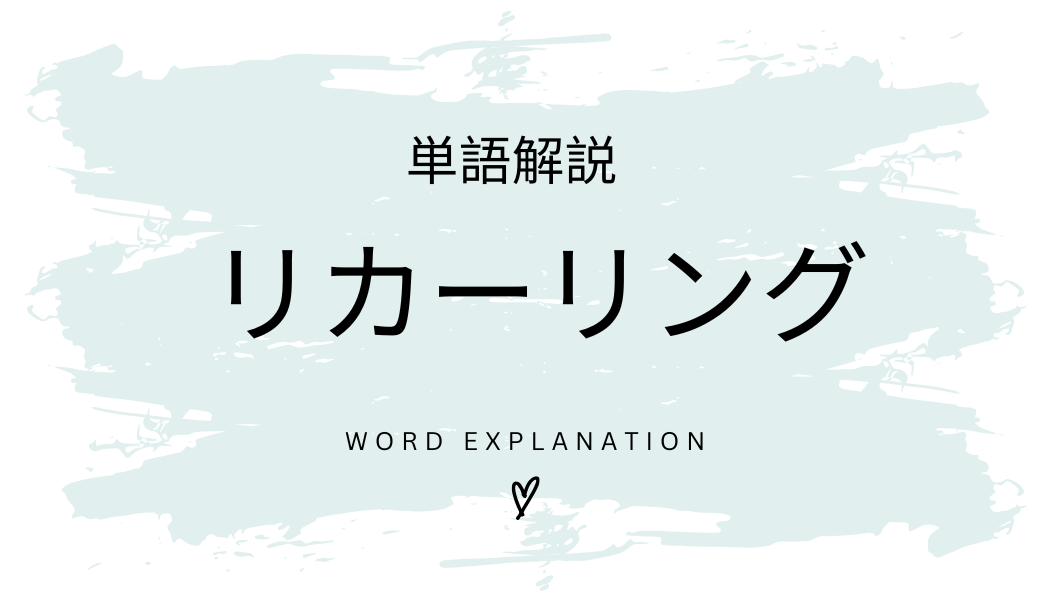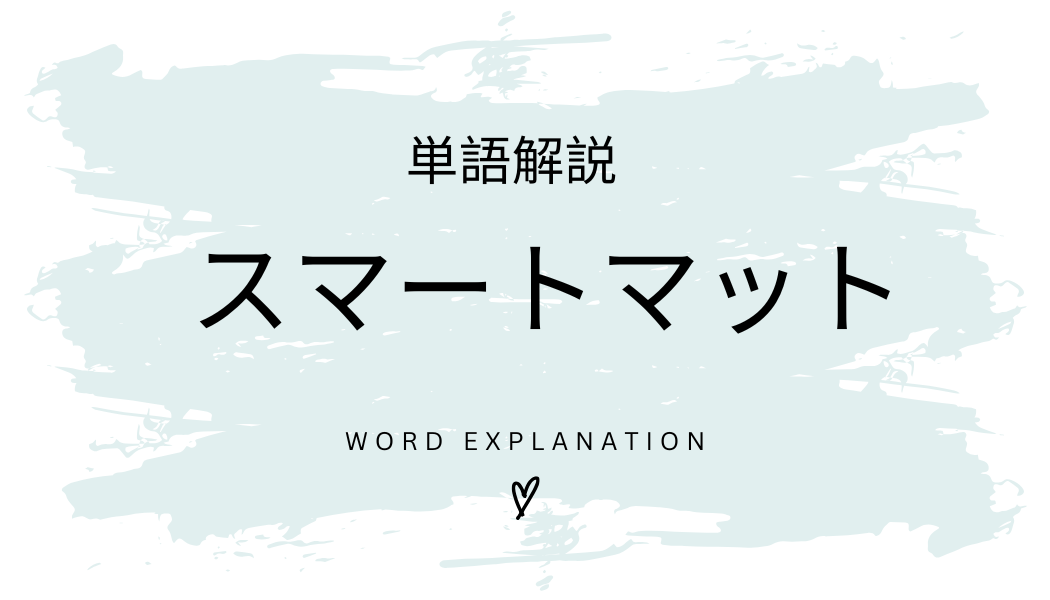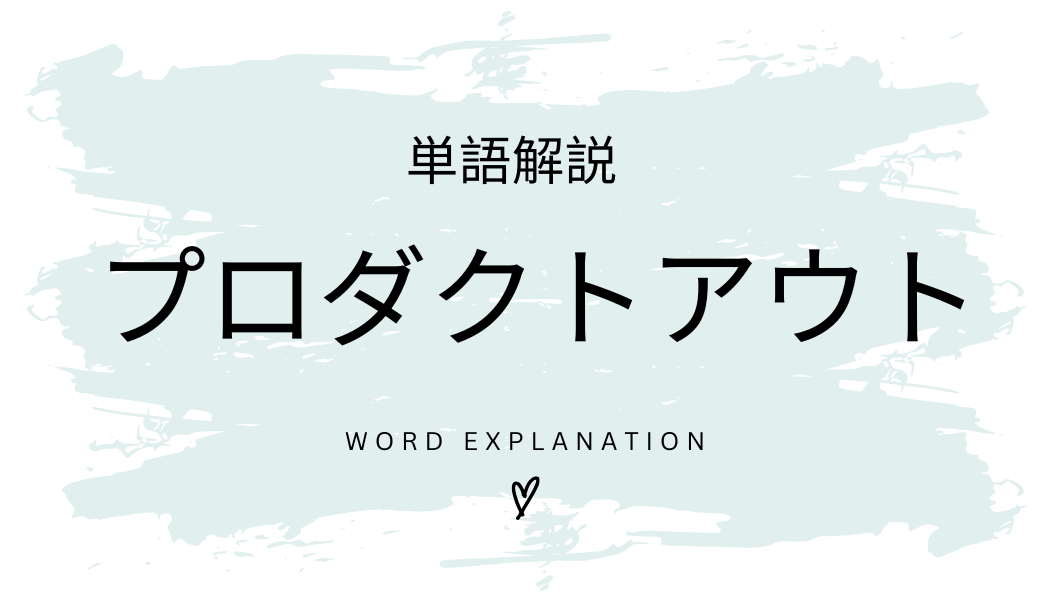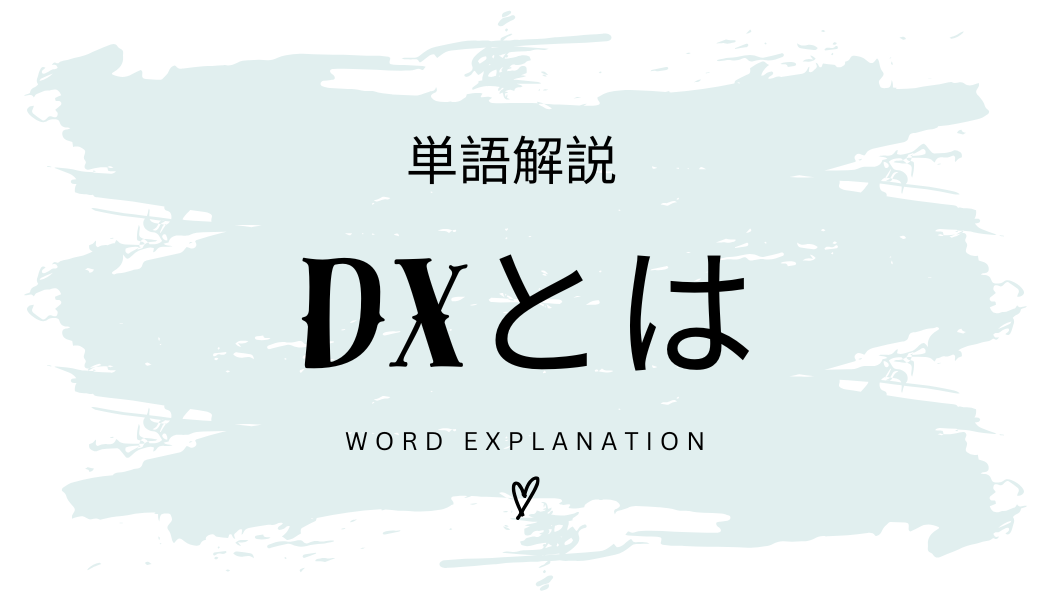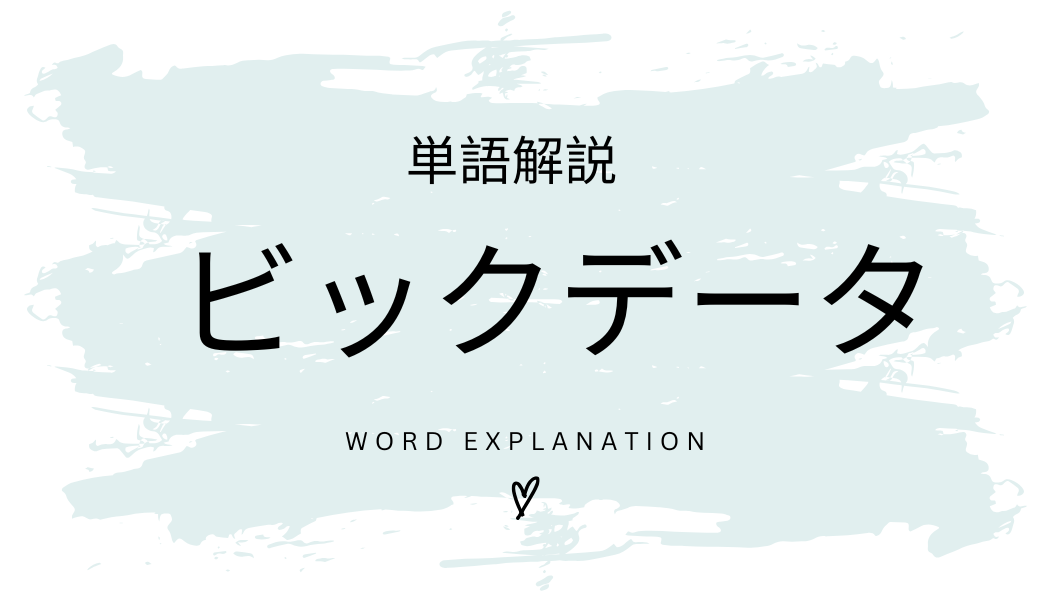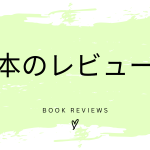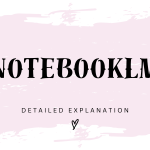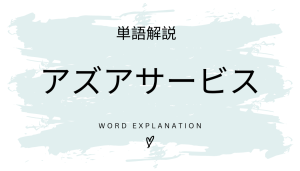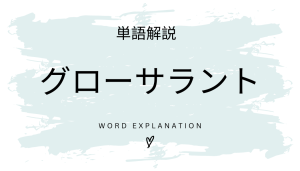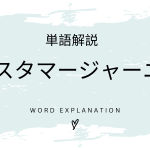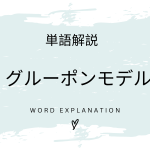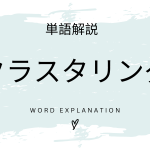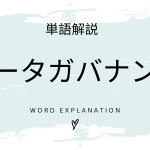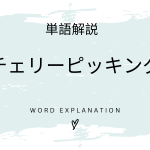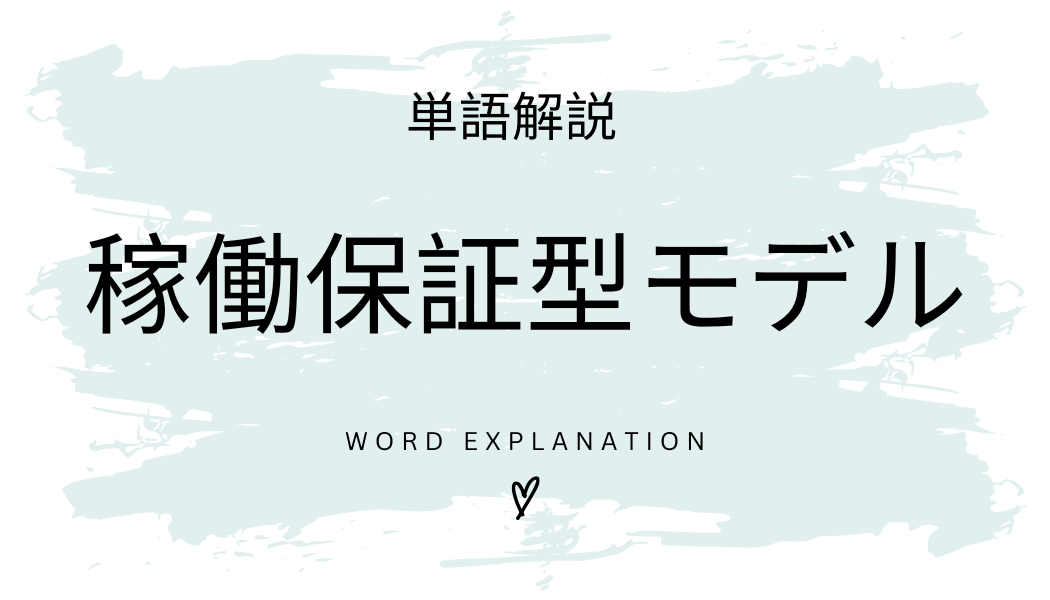
稼働保証型モデルとは?IT初心者でもわかる基本解説

DXママ
あいちゃん、ビジネスDX検定に出てくる「稼働保証型モデル」って聞いたことある?

あいちゃん
全然知らない!なんか機械が止まらないことを保証するってこと?

DXママ
それも合ってるけど、もう少し広い意味があるのよ。簡単に言うと「モノを売るんじゃなくて、そのモノがちゃんと働く(稼働する)ことを保証するビジネスモデル」のことなの。例えば、コピー機を買うんじゃなくて、「月に10万枚印刷できます」という稼働(サービス)を契約するイメージかな。

あいちゃん
へー!じゃあレンタルとかリースみたいなもの?

DXママ
レンタルやリースとは少し違うのよ。レンタルは単に物を借りるだけだけど、稼働保証型は「その機械がどれだけ成果を出せるか」という点まで保証するの。例えば、工場の機械なら「月に何個作れます」とか、建設機械なら「これだけの土を動かせます」とか。もし機械が壊れて稼働できなかったら、サービス提供側が責任を持って修理したり代替機を用意したりするわ。

あいちゃん
なるほど!契約した成果が出せなかったら提供側の責任になるんだね。これってどんな業界で使われてるの?

DXママ
製造業や建設業で多いわね。例えば、コマツという建設機械メーカーは「スマートコンストラクション」というサービスで、建設機械単体ではなく、工事全体の効率化を提案・保証するビジネスをしているわ。他にもコピー機のゼロックスやキヤノンも「1枚あたりいくら」という従量課金で、機械自体は無料や格安で提供する形に変わってきているの。

あいちゃん
なるほど!じゃあ買う側にとっては、初期費用が安くなって、ちゃんと動かなかったら提供側の責任になるからリスクが減るってことだね。でも売る側にとってはどんなメリットがあるの?
稼働保証型モデルのまとめ
稼働保証型モデルとは、製品そのものの販売ではなく、その製品が生み出す価値や成果(稼働)を保証し、サービスとして提供するビジネスモデルです。DXの進展により、IoTやAIなどのデジタル技術を活用して遠隔監視や予知保全が可能になったことで広がってきました。
稼働保証型モデルの特徴
- 製品からサービスへの転換:モノの所有から、その機能や成果の利用へとビジネスの軸がシフト
- 成果ベースの料金体系:使用時間や生産量などの成果に応じた従量課金が一般的
- 責任所在の変化:製品の稼働責任が顧客から提供者側に移行
- 継続的な関係性:単発の取引ではなく、長期的なサービス提供関係を構築
- データ活用:製品の稼働データを収集・分析して、サービス向上やさらなる価値提供に活用
代表的な事例
- 製造機器:生産量や稼働時間に応じた課金(例:工作機械メーカーのDMGモリ)
- 複合機・プリンター:印刷枚数課金(例:ゼロックス、キヤノン、リコー)
- 建設機械:土木工事の効率化を含めた総合サービス(例:コマツのスマートコンストラクション)
- エンジン:航空エンジンの飛行時間に応じた課金(例:ロールスロイスのPower-by-the-Hour)
- 照明:照明機器ではなく「明るさ」を提供するサービス(例:フィリップスのLight as a Service)
顧客にとってのメリット
- 初期投資の削減:高額な設備投資が不要
- リスク軽減:製品の故障や不具合は提供者の責任
- コスト予測の容易さ:使用量に応じた明確な費用計算
- 最新技術の享受:提供者側の更新により常に最新の技術を利用可能
- 専門知識不要:メンテナンスや管理の専門知識が不要
提供者側のメリット
- 安定した収益:一時的な販売収入から継続的な収益へ
- 顧客との関係強化:長期的な関係構築によるロイヤルティ向上
- 市場差別化:付加価値の高いサービス提供による競合との差別化
- データ収集:製品の使用状況データの収集・分析による製品改良
- 循環型経済への貢献:製品寿命の最大化や資源効率の向上
DXとの関連性
稼働保証型モデルはDXの重要な成果の一つです。IoTセンサーによる稼働状況の把握、クラウドでのデータ集約、AIによる故障予測など、デジタル技術の活用によって初めて実現可能になった側面があります。製造業のサービス化(servitization)と呼ばれる流れの中核となるビジネスモデルであり、多くの企業がDX推進の一環として取り組んでいます。