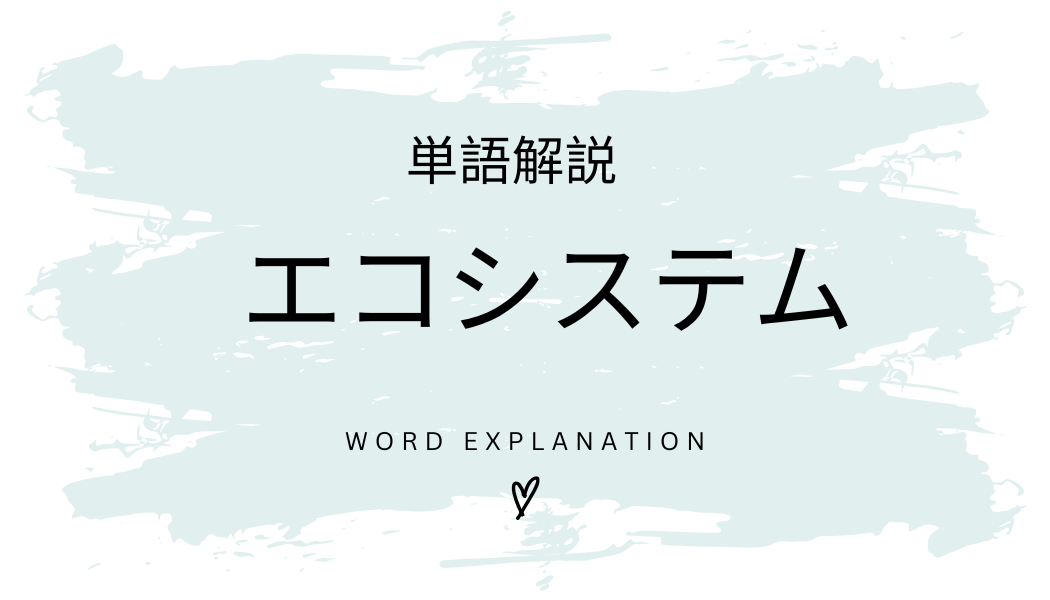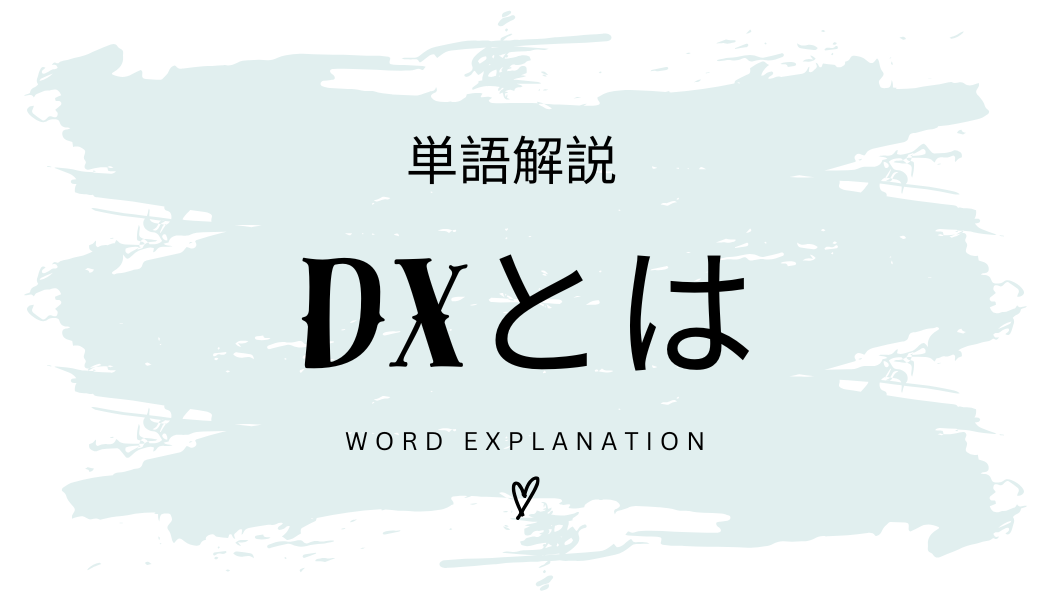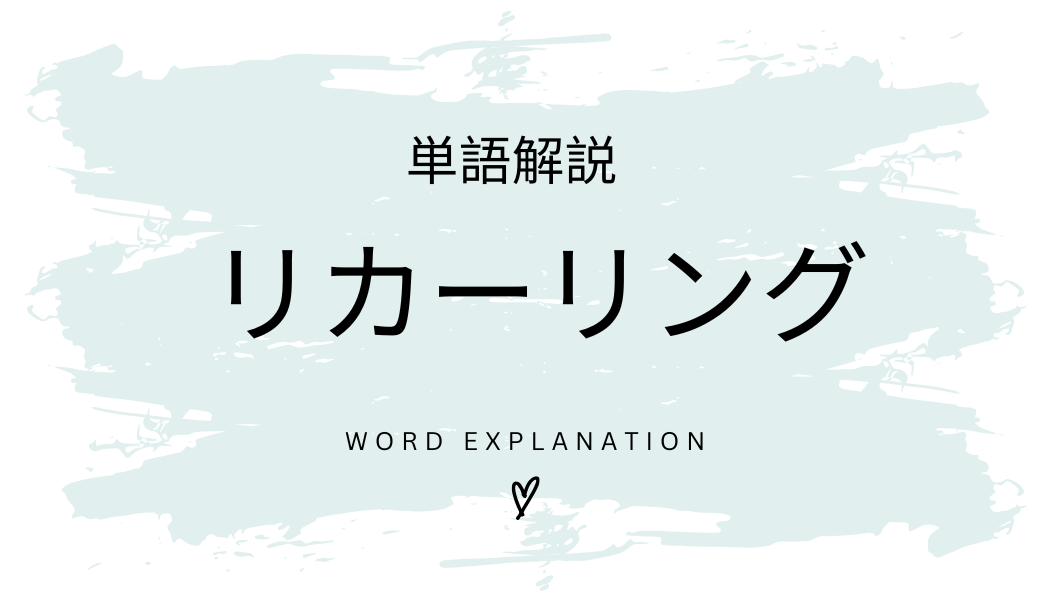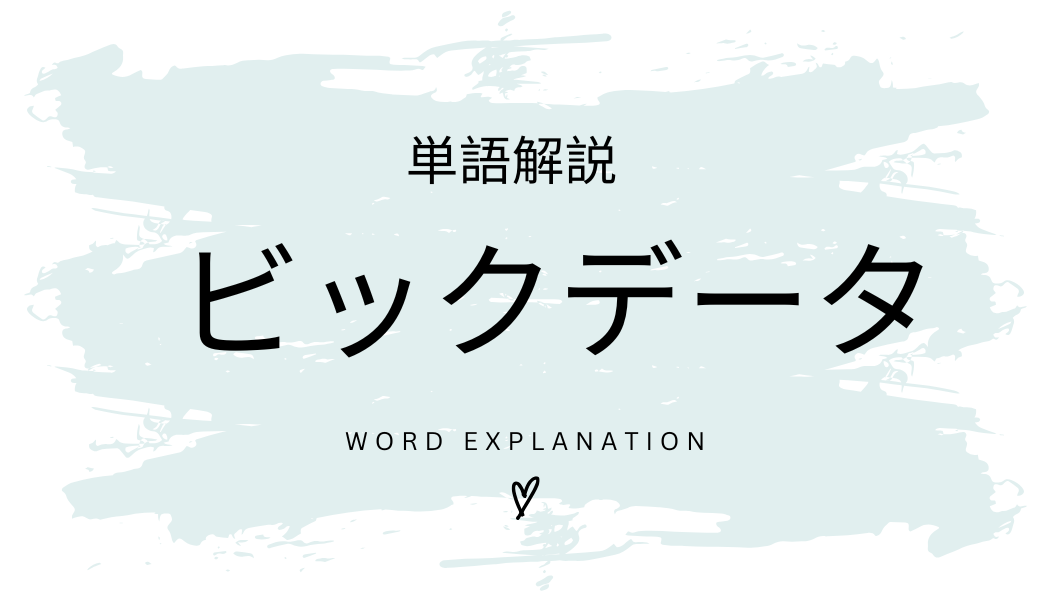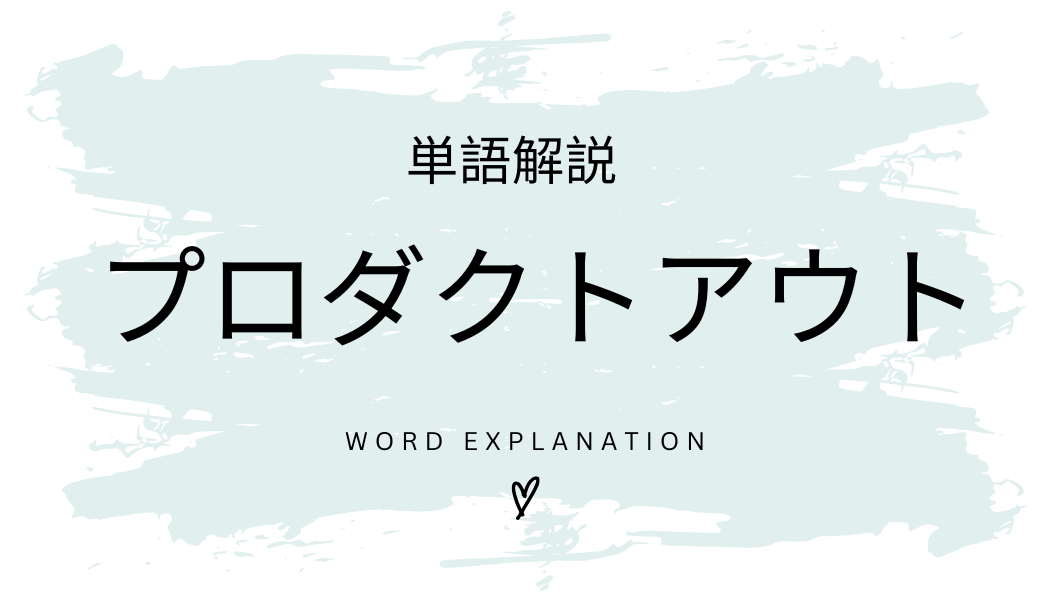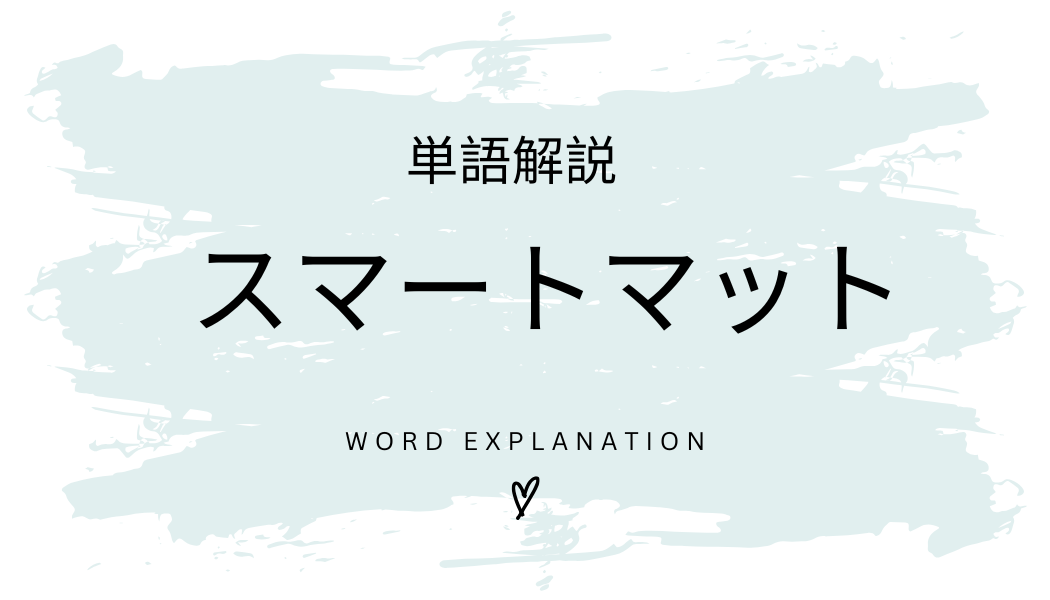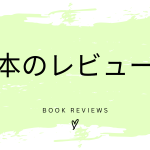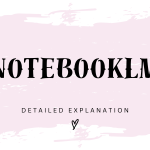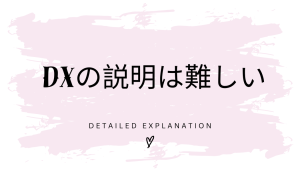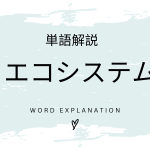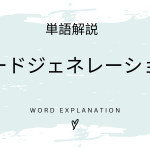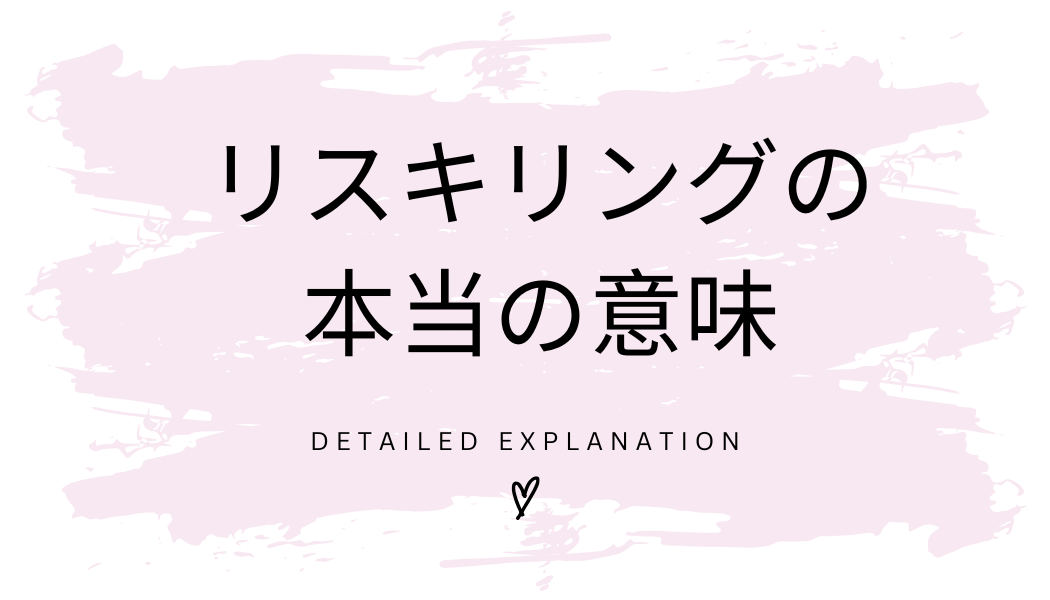



リスキリング講座を聞いて分かった本当の意味
先日、会社でリスキリングに関する講座を受講する機会がありました。講師は後藤宗明さん。この講座で聞いた内容が衝撃的で、私たちが普段「リスキリング」と呼んでいるものが実は誤解だらけだということがわかりました。
📝 講師プロフィール
後藤宗明(ごとう・むねあき)氏
早稲田大学政治経済学部卒業後、1995年に富士銀行(現みずほ銀行)入行。営業、マーケティング、教育研修事業を担当。2001年ニューヨークへ移住直後の9月11日、ワールドトレードセンターへの飛行機の衝突と崩壊を肉眼で目撃し、翌日からグラウンドゼロの救済ボランティアに参加。
リスキリングの本当の意味に衝撃
講座の中で一番心に残ったのは、「リスキリングは組織の責任であり、全てのリーダーとマネージャーの責任である」という点です。これまで何となく「自己啓発」や「学び直し」と同じような感覚で捉えていましたが、全く違う概念だったのです。
🔍 リスキリングの本質と誤解
リスキリングとは、英語の動詞「reskill」から来ており、「新しいスキルを習得させる」という意味です。本来は「組織が従業員をリスキルする」という使い方が正しく、単なる個人の自己啓発や学び直しとは異なります。
ハーバードビジネスレビュー特集「AI時代のリスキリング」
講座では、ハーバードビジネスレビューの特集「AI時代のリスキリング」についても紹介がありました。この特集では、リスキリングに関する5つの重要な観点が示されています。
- リスキリングは戦略上の必須事項である
単なる人材育成施策ではなく、企業が生き残るための戦略そのもの - リスキリングはすべてのリーダーとマネージャーの責任である
人事部門だけでなく、全てのマネージャーに責任がある - リスキリングはチェンジ・マネジメントイニシアチブの取り組みである
組織変革の一環として計画的に実施すべき - 従業員は理にかなっている場合は、リスキリングすることを望む
将来性が示されれば、多くの従業員は新しいスキル習得に前向き - リスキリングには村(エコシステム)が必要である
企業単独ではなく、教育機関や政府も含めた連携が必要
日本での誤解 - なぜ「学び直し」と訳されたのか
日本でリスキリングが「学び直し」と和訳されてしまったのには理由があります。これは2010年代の「リカレント教育」(反復・繰り返しの意味)に付けられた「学び直し」という訳が流用されたためです。
スキルアップとリスキリングの違い
講座では「スキルアップ」と「リスキリング」の違いも丁寧に解説されました。これも多くの人が混同している概念です。
スキルアップ(upskill)
定義:現在の延長線上でより高度なスキルを身につけること
リスキリング(reskill)
定義:全く新しいスキルを習得して新しい分野の仕事に就くこと
リスキリングの最終目標は「学ぶこと」ではなく「新しい分野の成長分野の仕事に就くこと」
他にも心に残った内容
1. 日本のデジタル化の遅れを実感
DXデジタル検定の勉強でも日本がデジタル化で世界から取り残されていることはよく出てきますが、講座でアメリカの自動運転の事例を聞いて、その遅れを実感しました。
サンフランシスコのロボットタクシー「Waymo」
講座では、サンフランシスコ市内で実際に運行されている無人自動運転タクシー「Waymo」の事例が紹介されました。完全無人の自動運転車が一般道を走り、乗客を運んでいるという現実に、参加者の多くが驚いていました。
日本では自動運転の話をすると「まだまだ先のこと」「実際は実現不可能でしょう」と言う人が少なくありません。しかし私は、自分が老人になる時には自動運転でないと困ります。できれば10年、遅くても20年で自動運転は実現してほしいと思っていましたが、講座を聞いて「できそうな感じだ」と思いました。よかったです。
2. スキル可視化とスキルの言い合っこ
講座では「スキルの言い合っこ」という方法も紹介されていました。スキルを可視化する際にこの方法を使うと、自己肯定感も上がるそうです。部署で取り上げたいと思いました。
スキルの可視化の重要性
組織内でのスキルの可視化は、リスキリングの第一歩です。自分のスキルや同僚のスキルを知ることで、組織としての強みや弱みが明確になります。これはハーバードビジネスレビューが指摘する「リスキリングには村(エコシステム)が必要」という点にも通じます。
まとめ:リスキリングを形だけで終わらせないために
この講座でリスキリングの本質を理解することができました。うちの会社も方針を示しているのは素晴らしいと思います。
ただ、方針を示すだけでは足りません。正直に言うと、方針や仕組みだけで終わるのがうちの会社の特徴なので、その先の実行部分に力を入れてほしいと思います。
リスキリングを絵に描いた餅にしないために
スキルを可視化することばかりに力を入れて、絵に描いた餅にならないでほしい。単に研修を受けさせて資格を取らせるというレベルで終わってしまっては、真のリスキリングにはなりません。
どうリスキリングする?研修を受けさせて、資格を取らせるなんてところで終わらないでほしいです。ハーバードビジネスレビューが指摘するように、これは「チェンジ・マネジメントイニシアチブ」であり、単発の研修で終わるものではありません。
偉そうに書いていますが、自分がマネージャーではないから言えることかもしれません。「じゃあ、お前がやれよ」と言われたら、リスキリングの実践は確かに難しいだろうなと思います。
この講座を通じて「リスキリングは単なる個人の自己啓発ではなく、組織の戦略と責任」という本質を理解できたことは大きな収穫でした。これから会社のリスキリング方針を見守りながら、自分自身もできることから始めていきたいと思います。
まとめ:真のリスキリングに向けて
リスキリングとは:
- 個人の「学び直し」ではなく、組織が従業員に新しいスキルを習得させる取り組み
- 単なる研修ではなく、組織の戦略と連動した人材育成・配置の仕組み
- ハーバードビジネスレビューが示すように、村(エコシステム)全体で取り組むべき課題