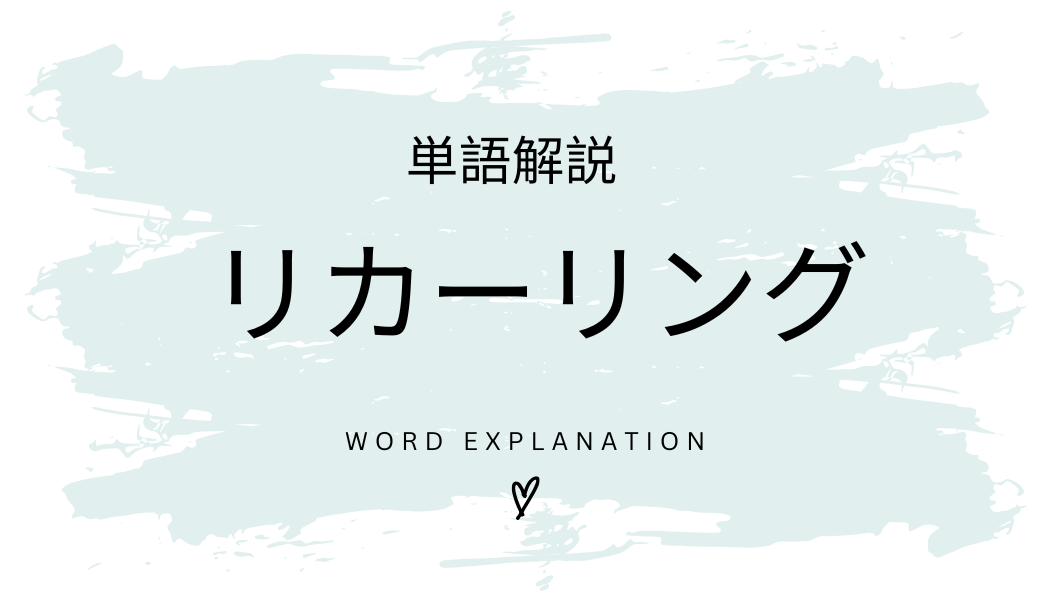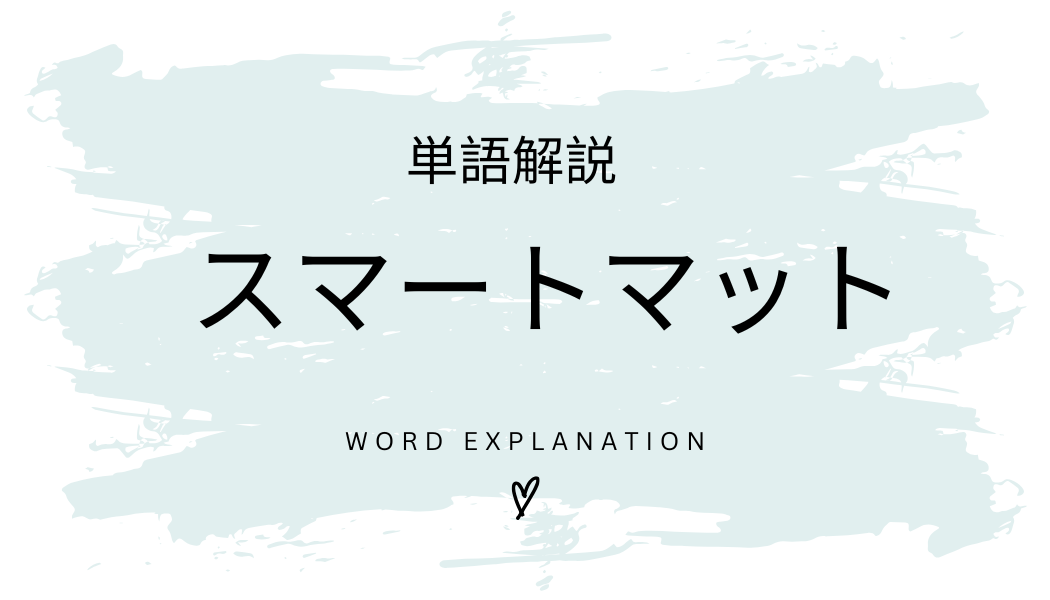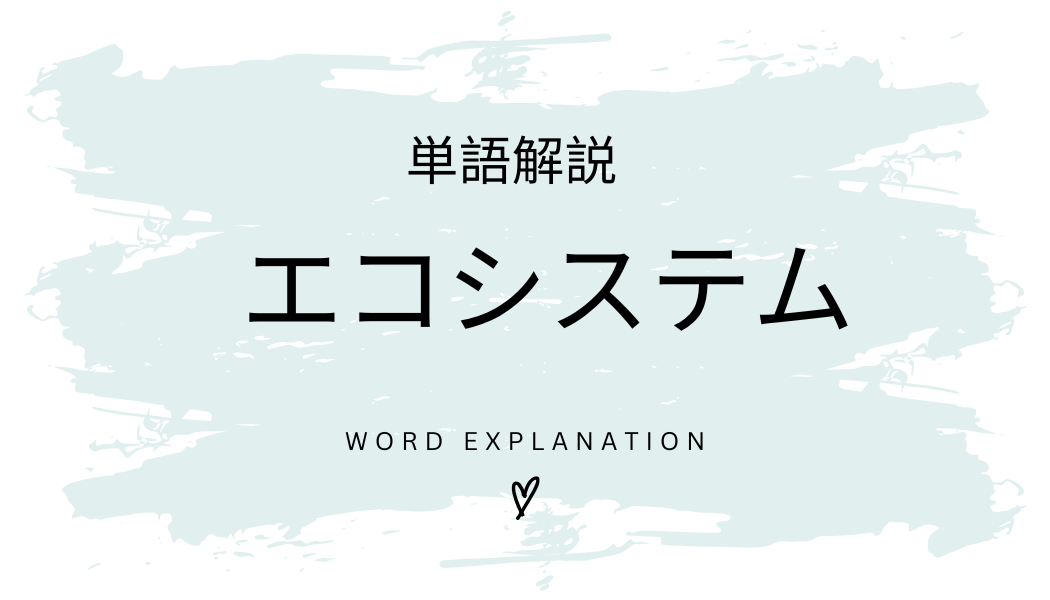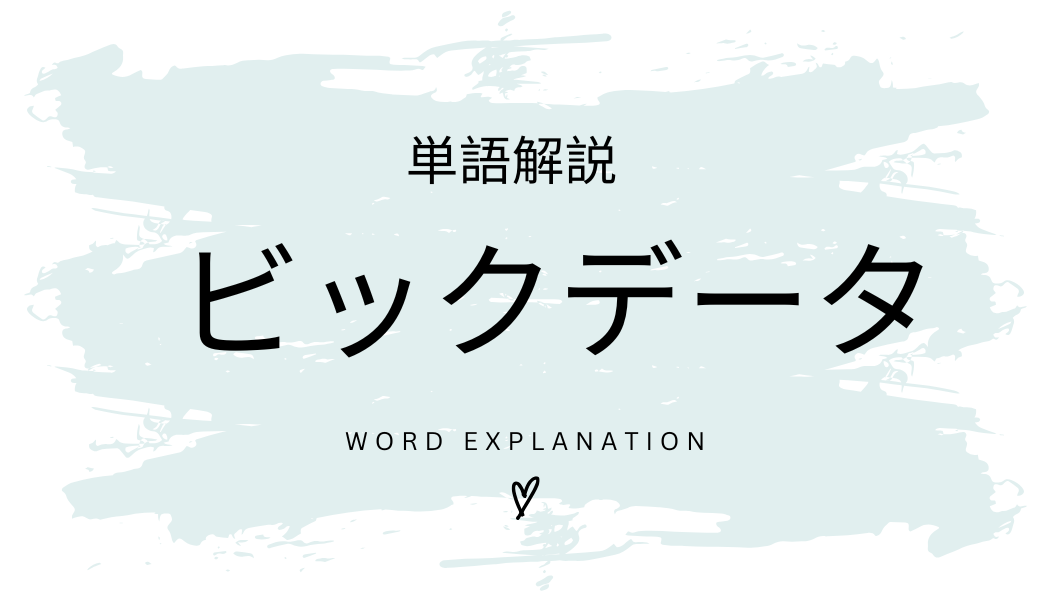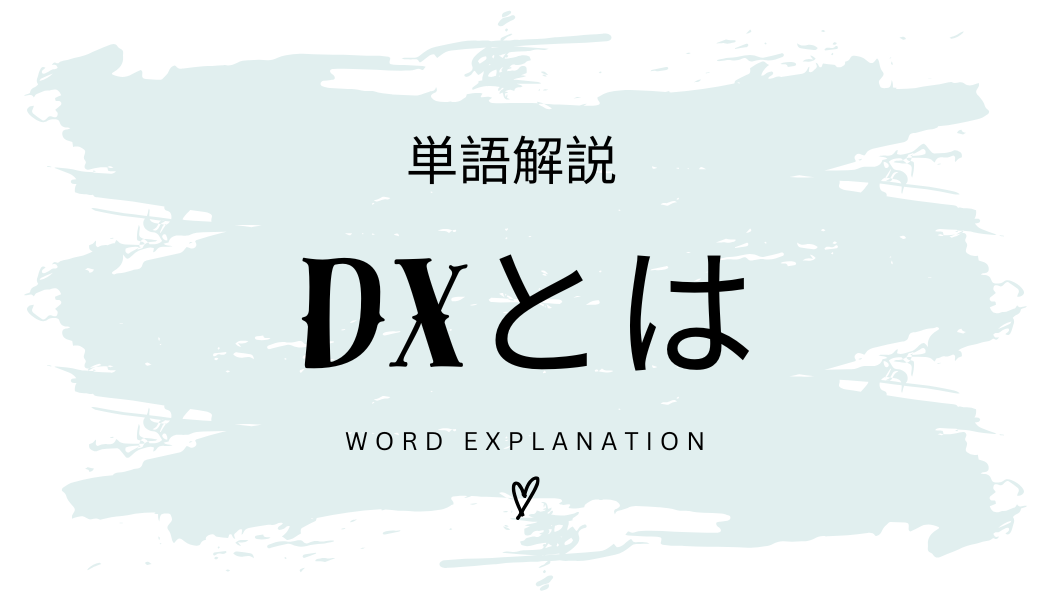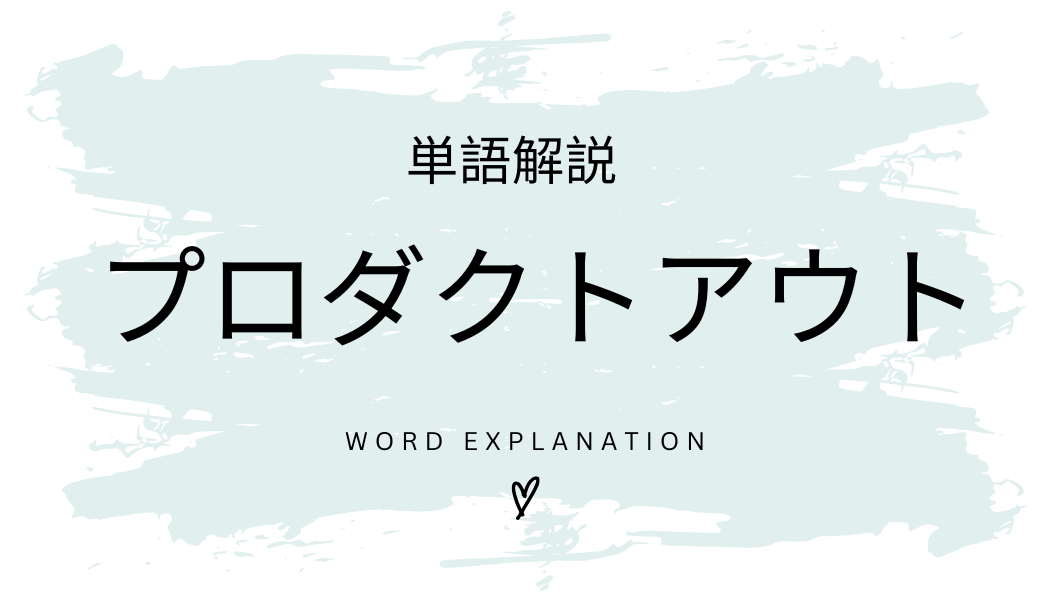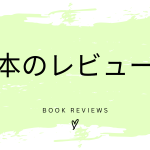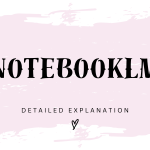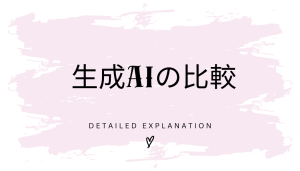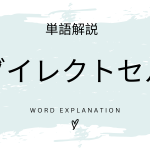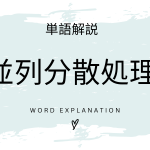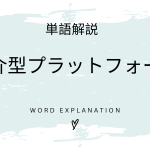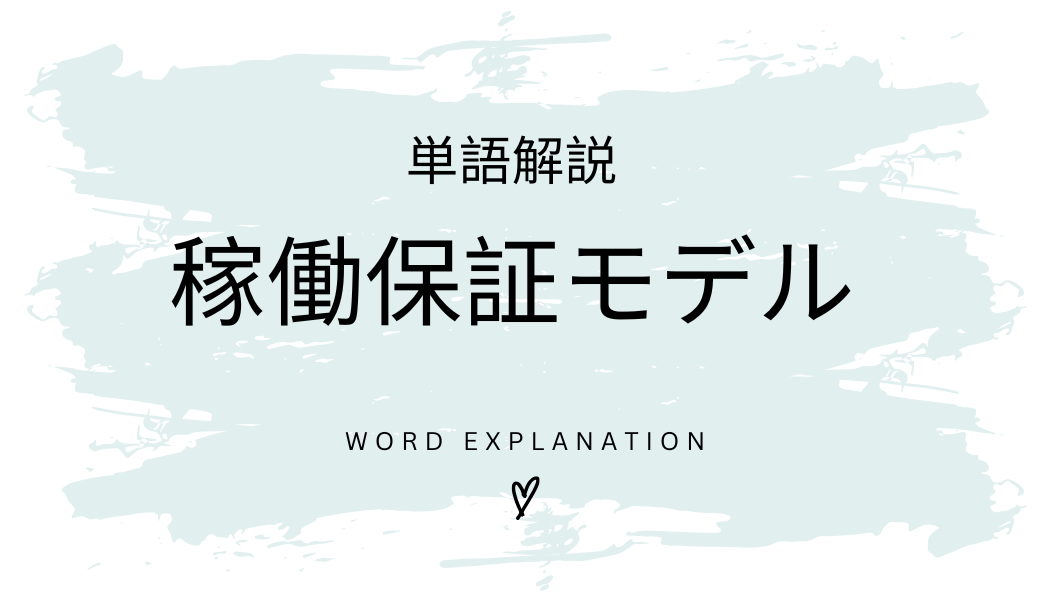
稼働保証モデルとは?IT初心者にもわかる簡単解説

DXママ
最近ね、会社のビジネスモデル検討会で「稼働保証モデル」って言葉が出てきたんだけど、あいちゃんは知ってる?

あいちゃん
それ、初めて聞いた!何か難しそうな感じだけど、どういう意味なの?

DXママ
簡単に言うと、コンピュータや機械などの製品を単に売るんじゃなくて、「ちゃんと動いている状態」をサービスとして提供するビジネスモデルよ。顧客は製品そのものじゃなく、その製品がきちんと稼働することに対してお金を払うの。

あいちゃん
なるほど!じゃあ、モノを買うんじゃなくて、そのモノの「動き」や「働き」を買うってこと?何か具体的な例はある?

DXママ
そうそう!例えばIBMっていう大きなコンピュータ会社は、昔からコンピュータを売り切りじゃなくて、利用した分だけ料金を払う契約にしてるの。航空機エンジンのロールスロイスも同じで、エンジンの出力と使用時間に応じて料金を払うサービスを世界中で提供してるのよ。

あいちゃん
へぇ!そうなんだ。でも、普通に買うんじゃなくてなんでそういう契約にするの?どんないいことがあるの?

DXママ
顧客側からすると、大きな初期投資がいらないし、常に最新の状態や安定稼働を提供してもらえるのがメリットなの。提供する側は、単に製品を売って終わりじゃなくて、長期間にわたって収益を得られるし、顧客との関係も深くなるのよ。実は、お互いにとって良いことがたくさんあるんだ!

あいちゃん
なるほど!最近よく聞くサブスクリプションとか、月額制のサービスも似てるのかな?

DXママ
そうそう!今のクラウドサービスやSaaSなんかも稼働保証モデルの一種と言えるわね。例えばGoogleのクラウドサービスは、使った分だけ料金を払い、サービスの安定稼働が保証されてるでしょ?これも稼働保証モデルの考え方なのよ。単なる月額制と違うのは、顧客の「使用目的に合わせた」サービス提供と、長期的な関係構築を重視する点かな。
稼働保証モデルとは?わかりやすいまとめ
稼働保証モデルとは、コンピュータや航空機エンジンなどの機器や部品、それらに関する稼働支援、保守などのサービスを顧客が使用する目的に応じて提供し、顧客と長期的な関係を構築しながら収益を得るビジネスモデルです。
稼働保証モデルの主な特徴
- 製品からサービスへの転換:物理的な製品そのものではなく、その製品の稼働や機能をサービスとして提供
- 利用ベースの課金:使用量や稼働時間、パフォーマンスに応じた料金体系
- 長期的な顧客関係:単発の売買ではなく、継続的なサービス提供による長期的な関係構築
- 顧客目的に合わせたソリューション:顧客の使用目的や要件に合わせたカスタマイズされたサービス提供
- リスク共有:提供者と顧客がサービスの成功に対する責任を共有
代表的な事例
- IBM:コンピュータを売り切りではなく、利用契約で使用量に応じた支払い契約を採用
- ロールスロイス:航空機エンジンをエンジン出力と使用時間に応じた料金で世界1万3000以上の場所でサービス提供
- クラウドサービス・SaaS:AWSやGoogleなど、ITインフラやソフトウェアを使用量に応じて提供
- Xerox:コピー機を販売せず、コピー枚数に応じた課金モデルを先駆的に導入
- 設備機器のリース:産業機器などを所有せず、稼働保証付きでの長期リース契約
導入メリット
- 顧客側のメリット:
- 初期投資の削減と費用の平準化
- 常に最新技術や状態へのアクセス
- 専門的な保守・運用サポートの獲得
- 予測可能な運用コスト
- 自社のコア事業への集中
- 提供者側のメリット:
- 安定した継続的な収益源の確保
- 顧客との長期的な関係構築
- 顧客ニーズへの深い理解と製品改善
- 競合との差別化
- 予測可能なビジネスモデル
注意点
- 契約内容の明確化:サービスレベル合意(SLA)や保証範囲の明確化
- 長期コスト計算:長期的には購入より高くなる可能性の検討
- サービス依存リスク:特定のサービス提供者への依存度が高まるリスク
- 変化への対応:ビジネス要件変化に対する契約の柔軟性確保
稼働保証モデルは、単なるサブスクリプションモデルとは異なり、顧客の使用目的に合わせたサービス提供と、長期的なパートナーシップを重視します。デジタル化が進む現代において、さまざまな業界で「所有」から「利用」へのシフトが進む中、このビジネスモデルの重要性はますます高まっています。